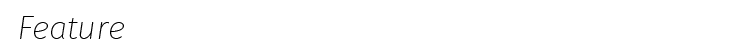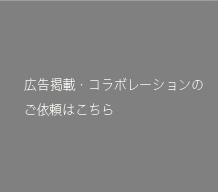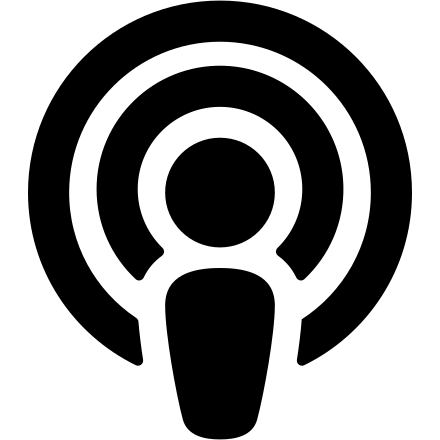語られてこなかった重文51点の“認定までの裏側“を暴く!「重要文化財の秘密」
東京国立近代美術館では、3月17日(金)から5月14日(日)まで、東京国立近代美術館70周年記念「重要文化財の秘密」が開催中だ。「『問題作』が 『傑作』になるまで」とキャッチコピーが冠された今回の展覧会は、ただの名品展に留まらない。時代とともに移り変わる日本の美術界の評価の変遷を追うことができる、美術史から考察する名品展となっている。
作品横の「ひみつ+α」の解説は必読であることはもちろん、余裕があればクイズも盛り込まれた音声ガイドとあわせて鑑賞することをおすすめする。

狩野芳崖《不動明王図》
会場に入ってすぐ目に留まったのが、狩野芳崖の《不動明王図》(4月2日まで)。題材はお馴染みの不動明王ではあるが、いつもよりも立体的なさまに、西洋の影響が見て取れる。この作品が、なぜこの展覧会の頭を飾ったのか。それは、全ての作品を見終わったあとに腑に落ちた。
「問題作」とも称されたのちに、重要文化財として指定された作品の数々を読み解いていくと、従来の伝統的な日本美術と、明治以降に普及していった西洋美術の間で、耐えず作品の価値基準が揺れ動いてきたことがよくわかる。今回の展示作品の数々は、もちろん伝統的な日本美術の「らしさ」を踏襲することはあっても、常に新しい価値観を持って美術史を引っ張っていこうする作家の心意気を持って、重要文化たる理由というものをアップデートさせてきた。このように、この不動明王図も、美術の受け手の価値判断が、前の指定作品や、他国の文化の往来などによってよりフレキシブルなものへと変化していったことで、指定の印を押されることなったのだろう。

横山大観《生々流転》展示風景
横山大観の《生々流転》は、全長40mの長さを誇る、今回の展覧会でも目玉作品のひとつだ。一滴の水が川の渓流を流れて、海へと注ぎ、龍となって天に登るというストーリーを、墨の濃淡や筆致で、綿密に、ドラマティックに描いている。山際の輪郭の内側をハケでぼかしている「片ぼかし」という技法や大観のお家芸である、独特の大気表現「朦朧体」などが多分に盛り込まれいるのが見どころだ。
数十年、数百年という単位で移り変わっていく自然は、人間の時間軸では体感することは難しい。しかし、この作品に沿って歩みを進めていくと、その計り知れない時の流れを、なんとなく理解できたような気持ちになる。
ちなみに、この作品の驚くべき制作年数についても、ぜひ音声ガイドのクイズに挑戦してみてから、正解を知ってほしい。

川合玉堂《行く春》
《行く春》で川合玉堂が描いたのは、桜が豪華に散る晩春の長瀞。それまでは風景画というと人気の景勝地を描くのが定番だったが、彼は自然や人々への温かな眼差しを持って日常の中に題材を見出した。渓谷ごと切り取った船の風景は、まるで春の終わりを見届けているかのような視点を届けてくれる。近づいて横から見たり、全体を俯瞰してみたり、視点の角度を変えるだけで、印象がまた違って見えてくるのも面白い。
福田平八郎《漣》は、周りに並ぶ作品の中でもかなり異色の存在だ。名前の通り、きらきらと揺れ動く水面を、プラチナ箔の画面に群青一色の線で水面を描いた日本画は今見てもかなりモダンで、どこか北欧マリメッコのテキスタイルを彷彿とさせる。
作者の福田平八郎が、友人と釣りをしている時に、さざ波の一瞬のきらめきに心を奪われたことがきっかけで作られた作品だ。当時、「これは果たして絵と呼べるのか」と物議を醸したのだそう。確かに、日本は着物などに使われる和柄に代表されるように、自然の抽象化というものに慣れ親しんできた民族ではある。けれど、当時の美術の世界ではこの作品は今日でいうデザインのジャンルに分類され、その域を出ないものとして過小評価されていたため、1932年に制作されたが、重要文化財へ認定されたのは2016年だ。長い年月を経てようやく認められたという背景を踏まえると、重要文化財の重みがまた違ってくるのではないか。

原田直次郎《騎龍観音》
《騎龍観音》の作者、原田直次郎はドイツで油彩画を学んだこともあり、観音像という東洋のモチーフを、西洋の技法を取り入れて描き上げた。こちらも、当時は、リアリティのありすぎる画風が、観音図らしくないと物議を醸した作品である。欧米化の進んだ明治20〜30年代は、日本美術を再考しようとする機運が高まった年でもあり、そんな時代背景の中で彼が選んだのは、異なる国の技法とモチーフをミックスさせるという、異端な取り組みであった。西洋画をアカデミックに学んだ彼は、日本の宗教画に自身がどんな影響を及ぼしうるのかを常に模索していたのだろう。
慣れ親しんだ観音様が、いつもとは違う艶美な印象を見せているのは、西洋的な奥行きのある描き方のせいか。平面的な観音様の表情もいいが、陰影のある描き方だと、より親しみが持てるように感じる。

萬鉄五郎《裸体美人》
一瞬で、「これは日本のマティスだ……」という感想がこぼれた、萬鉄五郎の《裸体美人》。フォービズムやそれに影響を与えたと言われるゴッホの影響を見ることができる。鮮やかな色彩で描かれた背景にゆったりと寝そべる女性。気品がありながらも、平坦な画風もあいまって、ゆるい表情でこちらを見ているのがたまらない。東京美術学校(現東京藝術大学)で、黒田清輝の元で学んだ萬は、留学経験はないものの、フォービズムといったヨーロッパの新しい芸術トレンドを入手すると、卒業制作としてこの技法を取り入れた。しかし、結果は19人中16番目。西洋のアカデミックな教育を受けてきた黒田にとっては、いささか気に入らない部分があったのかもしれない。個人的には、会場で販売されているこのアイコニックな女性をモチーフとしたグッズも、あわせておすすめしたい。

新海竹太郎《ゆあみ》
体をわずかに捻って、湯を浴びる女性、新海竹太郎の《ゆあみ》。髪型からもモデルは日本の女性であることがわかるが、西洋的な裸体表現が斬新な一作。それでいて、どこか控えめな動作を捉えているのが、日本らしい。肌に張り付く手ぬぐいの質感も美しいこの作品、実はこの手ぬぐいは、官設の展覧会「文展」の第1回目に展示されたということもあり、裸体表現への無理解を掻い潜るための策だっだという。そんな苦渋の策だったとはいえ、肌が透けるように纏われたこの布の質感を見事に表現している部分に、作者の技術の高さがうかがえる。

宮川香山《褐釉蟹貼付台付鉢》
内側に窪まったいびつなデザインに、流しかけられた釉薬の流れと、リアルな渡蟹の装飾で、器という静物に命が宿ったかのように思える、宮川香山の《褐釉蟹貼付台付鉢》。香山は、1876年のフィラデルフィア万博以降、海外の博覧会でもその名を轟かせた。この超絶技巧を駆使したダイナミックな装飾こそ彼の持ち味で人気を博したが、次第に過度な装飾は時代遅れとなり、シンプルな磁器もつくるようになる。本展では、宮川香山の超絶技巧陶芸と、シンプルな磁器、どちらも見ることができる。
最初の2作品を除き、今回紹介した殆どの作品は2000年代以降に認定されたという。重要文化財がなぜ重要とされたのか、それだけでなく、どんな経緯で、いつ重要と認められたのか。そこに着目するだけでも、作品の面白みがまた違ってくるだろう。
文=荒幡温子
写真=新井まる
【展覧会情報】
東京国立近代美術館70周年記念展 「重要文化財の秘密」
会期|2023年3月17日(金)~5月14日(日)
会場|東京国立近代美術館
住所|東京都千代田区北の丸公園3
開館時間|9:30〜17:00、金曜・土曜は20:00まで(入館は閉館30分前まで)
休館日|月曜日(5月1日、5月8日は開館)
料金|一般1,800円、大学生1,200円、高校生700円