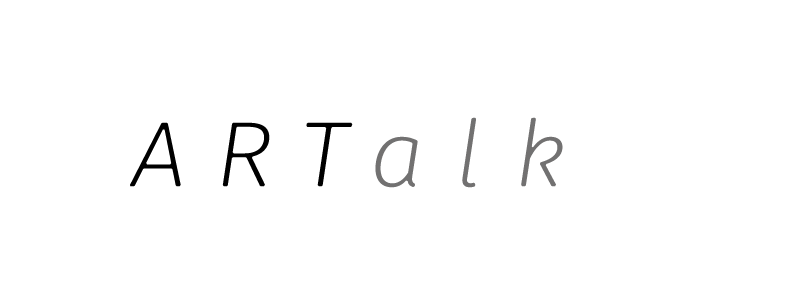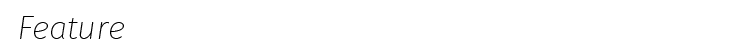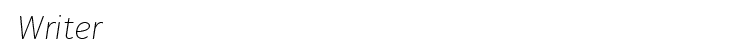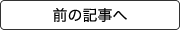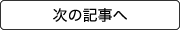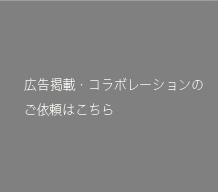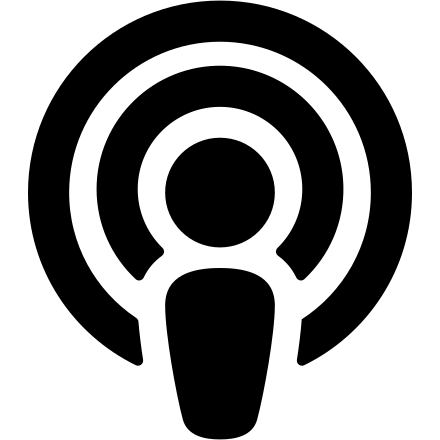「岡﨑乾二郎 而今而後 ジコンジゴ Time Unfolding Here」東京都現代美術館で7月21日まで
造形作家・岡﨑乾二郎の東京初となる大規模個展「岡﨑乾二郎 而今而後 ジコンジゴ Time Unfolding Here」が、東京都現代美術館で7月21日まで開催されている。岡﨑は1955年東京生まれ、1981年の初個展「たてもののきもち」で早くも注目を集め、その後40年以上にわたり多彩な活動を展開してきた。彫刻や絵画にとどまらず、メディアアート、建築、環境計画、ロボット開発にまで及ぶ幅広い創作活動は、常に先鋭的な視点を持ち続けている。国際的評価も高く、1982年のパリ・ビエンナーレ招聘以来、世界各地の展覧会に参加。近年はパリや韓国での個展開催など、国際的な注目度が一層高まっている。
岡﨑が脳梗塞に襲われたのは、2021年のこと。懸命なリハビリを経てほぼ回復したが、この生死の境をさまよう経験は、彼の身体認識と芸術創作に根本的な変化をもたらし、自身は2021年以降のこの変化を「転回」と呼んでいる。
本展では、この「転回」前後の作品を対比的に配置されている。1階では2020年までの代表作とシリーズを網羅し、3階には「転回」後の2022年以降に制作された新作・近作約100点が並ぶ。また、その間にある中2階には、入院中に描かれた貴重な作品も展示され、芸術家の変容の過程を辿ることができる。
本展タイトルの「而今而後」(ジコンジゴ)は、孔子の『論語』から引用された言葉だ。「これから先も、ずっと先も」という意味を持ち、死の淵に立った岡﨑の「自分がいなくなっても世界は続いていく」という深い洞察が込められている。

展示風景より、左は《おかちまちd-3》(1987-1989)
まず会場1階に足を踏み入れると、岡﨑の初期の代表作である、軽量なポリエチレン素材を切断し、折り曲げ、色彩を施した小さな立体作品群、「あかさかみつけ」シリーズが鑑賞者を迎え入れる。同シリーズはその他にも《そとかんだ》《おかちまち》《かっぱばし》といった、東京の地名の平仮名タイトルが付けられたものが展開されている。
“ゲシュタルト(形態)が強ければ、素材(ゴミ箱の紙屑であれ)やスケールにかかわらず、周囲からくっきり際立った領域として現れる”といったことを意図したこのシリーズは、立体構造が生み出す独特の空間性とタイトルから、その地名に基づいた個人的な経験を想起させることもあるだろう。一方で、展示のため輸送された作品が紛失したこともあり、作品がゴミ箱の中から発見されたエピソードについて岡﨑は、作品の効果については“壁にかけられている限りである”と言葉を添える。
これらの初期作品は、後の多彩な創作活動へと発展していく岡﨑芸術の種子が宿る貴重なもの。固有の形を模索し、言葉と造形の関係性を探求する岡﨑の根源的な問いかけが、これらの素朴な立体物から始まったことを実感することができる。

展示風景より、《Blue Slope》(1989)
金属製の大型立体作品《Blue Slope》と《Yellow Slope》は、1989年にベルギー・ゲントで開催された「ユーロパリア’89現代日本美術展」に出品された作品で、これらは「あかさかみつけ」シリーズの造形要素を抽出し展開させたもので、小さなポリエチレン素材で作られた「あかさかみつけ」シリーズと比較すると、サイズが格段に大きく、金属特有の硬質な質感と青と黄色の鮮やかな色彩が印象的だ。同じ造形原理から生まれながらも、スケールと素材の変化によって鑑賞体験が劇的に変容する点が興味深い。この対比は、岡﨑が一貫して追求してきた問題意識を浮き彫りにする。
人間はどのように物体の大きさや質感を認知するのか。造形の本質は維持されながらも、スケールと素材が変わることで、私たちの空間把握や身体感覚はどう変化するのか。鑑賞者は「あかさかみつけ」シリーズとこれらの金属作品の間に、どこに連続性を感じ、どこに差異を見出すのか。
単なる形態探究を超え、人間の知覚のメカニズムそのものへの問いかけとなっている。造形の本質とその変容の可能性を探求する岡﨑の思考を体感できる。

展示風景より
1992年以降、岡﨑乾二郎は本格的にアクリル絵具による絵画制作を開始する。一見、自由奔放に踊るような色彩のタッチで構成された作品は、即興的な印象を与えるが、実は作家が綿密に構築したルールに基づいて制作されている。キャンバス上に断片的に配置された、独特の立体感を生み出している色彩を注意深く観察すると、モチーフの類似性や反復、方向の転換、色彩の微妙な変調といった要素を発見できる。
さらに興味深いのは、鑑賞者が瞬きをしたり視点を移動させたりすると、絵画の見え方が変化すること。これは単なる視覚的な心地よさを超え、鑑賞者の認識そのものに働きかけ、複雑な視線による「見る」行為を能動的に促す仕掛けとなっている。これらをじっと眺めていると、色彩や平面的な差異にとどまらず、3次元的な位相空間、さらには量子力学における重ね合わせのような、私たちの認知を超えた現象の一端を見せられているような気分にさえさせられる。
また、岡﨑の絵画作品には、異様に長く物語性を帯びた独特のタイトルが付けられることも特徴の一つだ。これらのタイトルは一見すると作品と無関係な散文詩のようにも読めるが、実際に絵画と向き合うと、言葉と視覚表現の間に複雑な緊張関係や相互作用が生まれる。タイトルを読んだ後に絵画をどう見るか、あるいは先に絵画を見てからタイトルを読むとどのような体験が生まれるか。こうした見る順序によっても受容が変わる点も、この作品群の魅力である。

展示風景より、「四谷アート・ステュディウム」の資料
岡﨑は作品の創作だけでなく、批評家としても活躍し、『ルネサンス 経験の条件』や『抽象の力 近代芸術の解析』などの著作は芸術観に新たな視点をもたらした。また、広島県の「灰塚アースワーク・プロジェクト」や「なかつくに公園」の制作、四谷アート・ステュディウムの創設など、地域づくりや教育にも積極的に取り組んでいる。
会場では彫刻や絵画に加え、岡﨑が1990年代に広島県庄原市で手がけた総合地域づくりプロジェクト「灰塚アースワーク」や、2004年から2014年にかけて主宰した芸術の学校「四谷アート・ステュディウム」の関連資料も紹介されている。さらに、陶板タイル、ポンチ絵、ランドスケープデザイン、パブリックアートなど、多岐にわたる分野の作品や模型、映像資料が一堂に集められており、岡﨑の実践がいかに自在に領域を横断してきたかを明示する構成となっている。

展示風景より、自動描画装置の『T.T.T.Bot(Turning Table Tripod Robot)』
中2階では、岡﨑乾二郎が入院後まもなく描き始めた絵画作品に加え、およそ10年前に開発された自動描画ロボットが目に止まる。この装置は、ピカソをはじめとする著名な画家たちの描画プロセスをプログラムとして再現したもので、体験者は自らペンを動かすことなく、固定された手元を通じて画家たちの筆致の動きを追体験できる仕組みとなっている。これは、現在の生成AI時代を先取りするかのように、「作る主体」の可変性を問いかける先駆的かつ予兆的な作品であると言える。

展示風景より

展示風景より、《Lilies and roses, planted by long-departed Orthodox monks, wove through the garden where ferns advanced like silent armies. “The ancient Thracian gods still walk here,” the old man murmured, eyes gleaming. Beyond the flower-strewn ruins, cypress groves stretched toward horizon, harboring secrets of Cyclopes and Thessalian nymphs dancing in moonlight.》(2025)の一部
冒頭で触れたとおり、岡﨑は脳梗塞による麻痺からのリハビリを経て、自身の身体操作に対する意識が格段に高まったという。2021年以降の「転回」後の作品を紹介する3階では、岡﨑乾二郎が「転回」後に制作した大判の絵画群が一挙に展示されている。まず目に留まるのは、従来から続けられてきた複数パネルによる構成が、T字型を多く採用するようになった点である。また、キャプションには英語の長文が増え、変化が見受けられる。 絵肌はそれ以前より厚く塗り重ねられ、色彩はより明度が高く、透明感と光沢がある。突き合わされたカンヴァスどうし、カンヴァス を超えた展示室の壁、展示室空間とスケールの異なる境界が伸び縮みしながら展開する作品群は、展示空間が入れ子のような構成になっていることも相まって、作品が境界を超えて広がる、捉えようのないこの世界の一端に触れたような、何とも言いがたい感覚を覚える。

展示風景より
また3階ブリッジでは2005年頃から制作が開始された「ゼロ・サムネイル」シリーズも紹介されている。縦横20センチ前後の小型作品であるが、それぞれが古今東西の絵画や物語と密接に関係づけられており、示唆的なタイトルや、形状の異なる木製フレームとともに、元になった作品の存在を観客に推測させる構造をとっている。

展示風景より、左は《The souls of men still shine with heavenly fire/ひしめきあう庭の植物(かれの容貌)》(2020)
幼少期から粘土細工に秀でていた岡﨑にとって、彫刻はいつか本格的に取り組むべき仕事として常に心に内包していたものだった。病からの快復後、再び彫塑に取り組み始めた岡﨑は、以前にも増して精緻な表現を実現できるようになり、「拡大しても細部がどこまでも現れてくる」と語る通り、彫刻のディテールは格段に洗練されている。
実際に、1990年代の初期作品と近年の塑像群とを比較すると、ディテールの緻密さ、表面の情報量ともに著しく進化していることが見て取れる。本展では、いわゆる「転回」前後の彫刻作品の変化を体感できる構成となっており、岡﨑の創作の深化を追ううえで極めて示唆に富んだ展示となっている。

展示風景より

展示風景より、《Leading Ahead in the Dark, and Coming Out in the Day – More than Sunlight in Their Bodies/黑雲壓城城欲摧甲光向日金鱗開》(2025)の一部
本展クライマックスには、巨大な塑像作品群が待ち構える。これらの巨大彫塑作品は、岡﨑乾二郎が約30年ぶりに本格的に取り組んだ彫刻。粘土で成形した原型を高精細スキャナーで読み取り、拡大・出力して再構築したもので、外見こそ重厚だが、実は樹脂によって成形されている。技術的には簡単そうに見えるかもしれないが、表面の繊細なテクスチャーの再現には多くの試行錯誤を要したようで、外部の協力者と幾度も実験を重ねた末にようやく完成へと至った。
人間の身体をひねったかのような迫力ある造形に加え、表面各所に出現する解像度の異なる複雑なテクスチャは、距離によって見え方が異なるフラクタルな視覚的体験を鑑賞者にもたらす。
その一部にはゾウをモチーフにした具象彫刻もあるが、岡﨑は「果たして人はゾウ全体の姿を本当に捉えられるのか」という問いから出発し、実際に観察を重ねて形にした。ユーモラスなその姿態は、見る者に童心を呼び覚ますような魅力を放っている。岡﨑は「人体を超えるスケールの彫刻を作りたかった」と語り、「古代ギリシャの彫刻家が羨むような技術を駆使し、高解像度の表現を実現できた」と胸を張る。限界を設けず、他者との協働をいとわないその姿勢こそが、新たな挑戦を可能にした原動力である。

展示風景より、手前は《TELEPHANT/抽象の現象》(2025)

展示風景より、《Heaven’s Path Dim —Threads Rise to Light, Lines Seek the Deep》(2025)
本展では、造形を通じて人々の認識を揺さぶる岡﨑の「核心」に直接触れることができる。身体的困難を経た「転回」後の到達点は、観る者に大きな勇気と感動を与えるだろう。写真や言葉では到底伝えきれない迫力と精緻さが同居する展覧会に、ぜひ会場で対峙してみてほしい。
文=鈴木隆一
写真=新井まる
【展示会概要】
岡﨑乾二郎 而今而後 ジコンジゴ Time Unfolding Here
会期|2025年4月29日~7月21日
会場|東京都現代美術館
住所|東京都江東区三好4-1-1
電話|03-5245-4111
開館時間|10:00~18:00(展示室入場は閉館の30分前まで)
休館日|月、(7月21日は開館)
観覧料|一般 2000円 / 大学生・専門学校生・65 歳以上 1400円 / 中高生 800円 / 小学生以下 無料