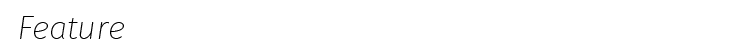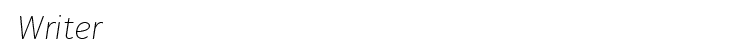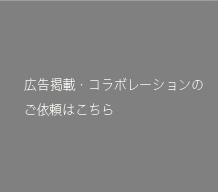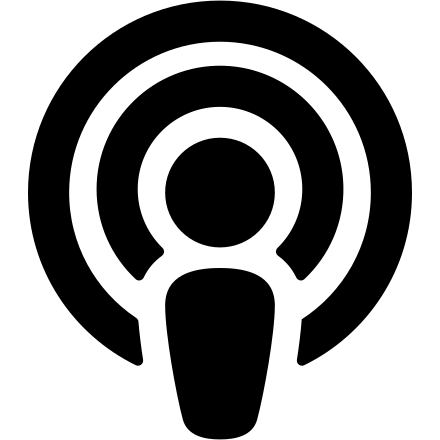「SIDE CORE 展|コンクリート・プラネット」都市を身体へと回帰させる実践の記録
タイトル画像:《under city(ver.2024)》
私たちが日々活動の拠点とし、巨大な生物のごとく代謝し続ける都市。多忙な現代社会において、その実態は表面的な部分しか見えず、手触りをもって捉えることは難しい。そんな都市の公共空間や路上を舞台に、数多くのアートプロジェクトを展開してきたアートチームSIDE COREの個展「SIDE CORE 展|コンクリート・プラネット」が、12/8(日)まで東京・外苑前のワタリウム美術館で開催されている。
彼らは、都市独自の公共性や制度に着目し、介入/交渉することで、幹線道路や鉄道、地下水路を特殊な手法で撮影した写真作品や、街灯やガードレール、道路工事の看板といった公共空間の要素を取り入れたインスタレーション、ネズミの人形が夜の東京をただひたすら歩く様子を記録した映像作品などを発表してきた。本展は、東京で初めてとなる大規模な個展であり、SIDE COREの代表的な作品を一堂に会する。「視点」「行動」「ストーリーテリング」という3つのキーワードを中心に、SIDE COREの作品が展示空間と共鳴しながら、都市文化がどのように連関し、広がっていくかを感じ取ることができる内容となっている。

展示風景より、カラー作品がナトリウムランプに照らされモノクロに見える
まずエレベータで2階に上がると、オレンジの光に包まれた空間に降り立つ。《モノトーン・サンセット》(2024)は、かつてトンネルなどで採用されていたナトリウムランプを用いた作品で、オレンジ色だけの光に照らされた物体は他の色が消えたオレンジ色と黒色のみモノクロ世界に還元される。本展の導入としての、アンダーワールドへの入口といった印象を受ける。

展示風景より、手前は《コンピューターとブルドーザーの為の時間》(2024)、奥は《夜の息》(2024)
続く吹抜け空間には、単管の鉄パイプで高速道路のジャンクションのように構成された《コンピューターとブルドーザーの為の時間》(2024)が設置されている。この鉄パイプの管の中には、セラミックの球が一定時間ごとに3階から落とされ、カラカラと音を立てながらウォータースライダーのごとくパイプを通過し落下していく。電柱のトランスが放つジリジリという音、マンホールから漏れる水の流れる音、車や電車が引き起こす振動で鳴る陸橋のキシキシという音など、普段は気づかない都市の環境音を模した作品であるが、閑静な美術館の中では大音量に感じる。
鉄パイプを照らすのは、複数の自動車のヘッドライトを用いた《夜の息》(2024)という作品。ヘッドライトは本来、前方を照らし視界を確保するためのものだが、並べてみると車種ごとにデザインが細かく異なることに気づかされる。かつてフランス車のヘッドライトが黄色で、パリの夜景は黄色に輝いていたが、今ではLEDライトが主流となっている。将来的に自動運転が普及すれば、ヘッドライトが不要となり、街が再び暗闇に包まれるかもしれないといった、自動車のパーツを通して街の変わりゆく風景を想起させる作品となっている。

展示風景より、《東京の通り》(2024)部分
回転機構によってゆっくりと回る壁の作品《東京の通り》(2024)は、工事現場で使用される注意書きやピクトグラムを壁一面にコラージュしたもので、人物がかぶるヘルメットの形状や、数字フォントのプロポーションの違いなど、細部に様々なバリエーションがあることに気づく。1964年のオリンピック以降、工事現場にも非常口マークに代表されるピクトグラムが多く採用されてきたが、標準規格がないため、街中には「似ているけれど少し違う」ピクトグラムやデザイン、素材の看板があふれている。本作は、そうしたさまざまなデザインの看板を収集し、切り出して並べることで、東京の都市景観の複雑さやゆがみを表現している。また連続するフォントはオノマトペ(擬音語)やマップ上の道路図にも見えるように複層的に配置されている。
《柔らかい建物、硬い土》(2024)は、土からつくられ土に分解されない人類初の産業廃棄物である焼き物の作品で、建築から日用品まで、都市空間と身体の接点となる物事をモチーフとしている。数万年前の土器が出土することは言い換えれば都市の記憶が否応なしに残り続けることの裏返しであり、人新世と言われて久しい現代社会は未来に何が残せるのかと考えさせられる。

展示風景より、手前《柔らかい建物、硬い土》(2024)

展示風景より、《unnamed road photographs》(2024)

展示風景より、《untitled》(2022)

展示風景より、《empty spring》(2022)
3階に移動すると、SIDE COREが2017年ごろからスマートフォンで撮影した写真をプリントアウトした《unnamed road photographs》(2024)が壁一面に並ぶ。各写真は明滅を繰り返し、鑑賞者がじっくりと見ることができない。これは、スマートフォンやSNS上で私たちが写真をスワイプしたり拡大したりしながら常に動的に見ていることに着想している。写真はSIDE COREの過去の活動を振り返るとともに、彼らが活動を続ける中で生まれた無数の即時的なイメージを垣間見ることができる。
《untitled》(2022)は、羽田空港近辺のトンネルで撮影された映像作品で、人物がトンネルの壁に肩を擦りながら歩く姿が映し出されている。歩行者がほとんど通ることのないトンネルの壁には、長年の汚れが蓄積しているため、人物のTシャツには自動車の排ガスで生じた煤(すす)がつき、壁には長い線が残る。この“肩の線”は、今でもトンネルに残っており、都市のディテールを身体を使ってスキャンし、都市空間を新たな視点で捉え直すというSIDE COREのテーマを鮮明に反映している。
《empty spring》(2022)は、コロナ禍の初期に東京で撮影された映像作品で、非常事態宣言下の東京という異常な時期を記録するものであり、人影が消えた街中で、ホウキやゴミ、三角コーンなどがポルターガイストのように動く様子が映し出されている。都市の風景を映し出すことは、ニュース映像や映画の中で無意識に撮影された風景が、後に貴重な資料となるように、常に変わり続ける“街の記録”としての価値を持つことがある。

展示風景より、《under city(ver.2024)》
4階で上映されている、2023年から継続しているプロジェクト《under city(ver.2024)》は、スケーターたちが都市の地下空間を滑走する様子を捉えた映像作品。壁面、床、天井に設置された5チャンネルのモニターで映像が切り替わり、共鳴する音響とともに鑑賞者を包み込む。撮影場所は、通常の都市生活では立ち入ることができない地下の廃駅や調整池、汚水処分場、雨水貯留施設など。フランス・パリの地下迷宮のカタコンベやアメリカ・NYの地下鉄の廃道など、世界中の都市には通常は入れない同様の地下空間が数多く存在しているが、それら未知への憧れや想像は私たちに都市へのより広い視座を与えてくれる。
映し出される映像はアンダーグラウンドに接続する劣化した配管内部の錆をとらえたものから、普段はアクセスできない公共の施設でスケーターたちがライドしたものまで、都市を多面的に捉え、公共性にアクセスしようとするSIDE COREの本質を象徴している。
さらに、本作では地下空間の3Dスキャンを行い、データをコラージュした3Dモデルも作品の一部となっているが、スケーターたちが背負っている作業照明によって照らし出され、スケートボートの摩擦音が反響する映像は、あたかも都市に潜む巨大なヴォイドを多面的にスキャンし、実態を露わにしているようにも見える。
2階から始まり上階へと続く屋内展示は4階で終わるが、周辺の屋外環境にも展示は広がりを見せており、内から外へと私たちの都市への想像力を喚起させる。美術館向かいのビルの屋上からは、《ねずみくん》(2018)が静かに変わりゆく街を俯瞰している。SIDE COREの身体性を伴った都市における実践を紹介する本展を、ぜひこの機会に体感していただきたい。

展示風景より、ワタリウム美術館向かいのビルからこちらを見る《ねずみくん》(2018)

展示風景より
文=鈴木隆一
写真=新井まる
【展示会概要】
SIDE CORE 展|コンクリート・プラネット
会期|2024年8月12日〜12月8日
会場|ワタリウム美術館
住所|東京都渋谷区神宮前3-7-6
電話番号|03-3402-3001
開館時間|11:00〜19:00
休館日|月(8月12日、9月16日、23日、10月14日、11月4日は開館)
料金|大人 1500円 / 学生(25歳以下)・高校生 1300円 / 小・中学生 500円