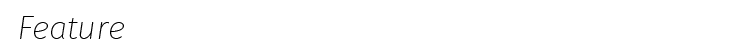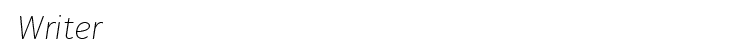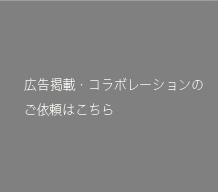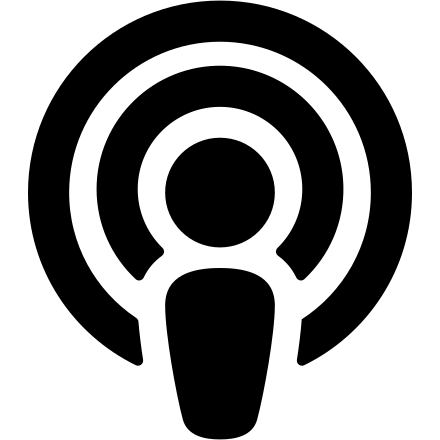60年間の時代の潮流と作品の軌跡。「李禹煥」展が国立新美術館で開催中
今年で開館15周年を迎える国立新美術館で、「もの派」を代表する現代美術家・李禹煥(リ・ウファン)の大規模回顧展「国立新美術館開館15周年記念 李禹煥」が開催されている。日本では2005年に横浜美術館で開かれた「李禹煥 余白の芸術展」以来17年ぶり、東京では初となる大規模な回顧展だ。「もの派」とは、1960年代末から1970年代後半までの日本の美術運動の名称。つくらないことを基本とし、自然や人工の素材を“あるがままのもの”として用い、近代的な造形原理を否定するという共通の考え方により、各作家は作品を展開した。
李禹煥は「もの派」の理論的支柱として、作品のみならず多くの論考を残してきた中心的存在だ。本展では、「もの派」にいたる前の視覚の問題を問う初期作品から、彫刻の概念を変えた〈関係項〉シリーズ、静謐なリズムを奏でる精神性の高い絵画など、李の仕事を網羅的に浮き彫りにしている。また、李が自ら展示構成を考案しており、屋外展示を分岐点に、彫刻と絵画の2つのセクションに大きく分かれている。それぞれのセクションでは時系列的に展示されているため、李の作品の変遷をよく理解できる構成となっている。

本展の開会式に出席した李禹煥
李禹煥は1936年、韓国南部地方の慶尚南道(キョンサンナムド)の人里離れた山奥で生まれた。幼少期から詩、書、画を学んだ李は、ソウル大学校美術大学東洋画科に入学した1956年の夏、病気の叔父に漢方薬を届けるために来日し、叔父のすすめでそのまま日本に残ることとなる。1957年からは拓殖大学で日本語を学び、翌年には日本大学文学部哲学科に編入、絵を続けながらもリルケやハイデガーなど哲学の研究をしていた。1960年代に入り、世界的にも若者の政治・社会運動への参加が活発であった中で、68年に開催された「トリックス・アンド・ヴィジョン 盗まれた眼」展(東京画廊と村松画廊)では、一種のトロンプルイユ(視覚のだまし絵)である作品「影」などでトリック・アートの動向を牽引していた高松次郎(1936-98年)ほかが出品されており、当時の李に大きな刺激を与えた。
李はその後、韓国人美術家・郭仁植(カク・インシク)(1919-88年)などと参加した同1968年の「韓国現代絵画展」(東京国立近代美術館)において、空間や見る者にハレーションを起こすほどの蛍光色が特徴的な3点1組の《風景I》、《風景II》、《風景III》を出品。この頃から「もの派」的な作品を試行し始め、新しい表現の論理を構築し、石とガラス、鉄板と綿、柱に木材をロープで縛り付ける作品などによって、すべては相互関係のもとにあるという世界観、ものともの、ものと人とが「出会う」関係性を見せるための作品を制作していくことになる。

《風景I》、《風景II》、《風景III》(いずれも1968/2015) 個人蔵(群馬県立近代美術館寄託)

手前:《関係項》(1968/2019)森美術館、東京、左奥:《第四の構成B》(1968/2022) 作家蔵、右奥:《第四の構成A》(1968) 作家蔵
もの派の出発点としては、しばしば1968年10月「神戸須磨離宮公園現代彫刻展」で発表された関根伸夫の《位相―大地》が取り上げられる。李禹煥はこの《位相―大地》との遭遇によって、「トリックス」の系譜ではなく「物の状態の変化」といったような独自の受け止め方に確信を得ながら、1969年8月に「現代美術の動向」展(京都国立近代美術館)で、〈関係項〉シリーズの中でも最初期の《現象と知覚A》、《現象と知覚 B》を出品した。無垢の鉄板の剛性や不透明性、対するガラスの脆性や透明性といった、素材の特性を対比的に用いることは〈関係項〉の特徴の一つ。鉄板の立方体に近い直方体の12辺から綿が膨張してはみ出した《構造A》には、この特徴が全面的に表れている。
そして、表現は作ることと作らぬこととの関係へと進展していく。自然石とそこから抽出して作った産業製品の鉄板の組合せによってものの在りよう、空間との関係に向かったのである。李は、観念や意味よりも、ものと場所、ものと空間、ものともの、ものとイメージの関係に着目した制作へと移行することとなる。1990年代以降には、李はさらにものの力学や環境に対しても強く意識を向けるようになり、石の形と鉄の形が相関する〈関係項〉も制作している。鉄板の一部をくり抜きその前に大きな石を置くと、さも石の力で鉄板が凹んだように見える(事実宇宙ではこのような現象が起こる)。より近年の作品では、環境に依存するサイトスペシフィックな傾向が強まっており、フランスのラ・トゥーレット修道院で発表された《関係項―棲処(B)》(2017年)はその典型である。
鉄板も鉄鉱石からできていることを考えれば、大きなくくりとして同じ石が形を変えて対峙していることとなるが、そこに流れる時間の歴史には差がある。自然の中で生まれた石は私たちの感覚からはかけ離れた長い年月をかけて生成され、風雨によって変形していったであろう。一方で、鉄板は人の手によって生成され、板という形に整形されている。ただし、何千万年の時からみれば、どちらも一時的な塊として姿を留めているにほかならない。それら変化に要した時間の異なる2つの石、さらには自己を含む周辺の間やそこにある時間を感じながら作品を眺めると、言葉で表現することを忘れてしまうような、リッチな体験が可能となる。そこにあるモノとの関係を感じ、ただそこにあること、人間のもつ原体験のような一体感を感じられないだろうか。

手前:《現象と知覚A 改題 関係項》(1969/2022) 作家蔵、右:《構造A 改題 関係項》(1969/2022) 作家蔵
奥:《項》(1984)神奈川県立近代美術館

《関係項―棲処(B)》(2017/2022) 作家蔵

《関係項―サイレンス》(1979/2005) 神奈川県立近代美術館
本展の彫刻と絵画の分岐点にあたる野外展示場には、ヴェルサイユ宮殿の丘の広場ではじめて製作されたステンレスのアーチ《関係項―アーチ》が本展に合わせて設置されている。李禹煥はヴェルサイユでの展覧会の際に、冬の長野でみた美しい虹の記憶にインスパイアされて本作をつくるに至ったそうだが、配置にあたっては、庭園建築家アンドレ・ル・ノートルが設計した庭と干渉し合わないように、隙間に置くことを意図したと過去に述べている。本展でも、アーチに直交するように長いステンレス板が地面に置かれ、鑑賞者がステンレス板の上を歩きながら頭上のアーチをくぐり抜けるたびに、周りの空間が改めて新鮮に見える展示となっている。
作品の内部や上を歩くという展示形式は、近年の李の作品に数多く見いだされる。《関係項―鏡の道》では、鑑賞者は鏡面仕上げの長いステンレス板の上を歩きながら、鏡面に映る周囲の風景の移り変わりを体感する。鏡面仕上げのステンレスは、近年「無限」の概念に強く関心を寄せる李にとって重要な素材だ。美術館入口に展示されている《関係項―エスカルゴ》は、高さ2mのステンレスが、渦巻状に曲げられた作品。中心付近では、鏡面に反映される自身の姿が映し出され、自分がいる場所を見失うかのような感覚に襲われる。

《関係項─鏡の道》(2021/2022)作家蔵

《関係項─エスカルゴ》(2018/2022) 作家蔵
《関係項―アーチ》をくぐり抜け、新鮮な気持ちになったところで、展示は後半の絵画のセクションへと続く。1971年、李禹煥は3ヵ月ほどヨーロッパで過ごしたあと、アメリカ経由で帰途につく。ニューヨーク近代美術館で開催されていたバーネット・ニューマンの没後初の個展を観て刺激を受けた李は、幼少期に学んでいた書道の記憶を思い起こし、絵画への関心を深めていく。 そこから生まれたのが、はじめは濃い色がだんだん薄れてゆく過程を表わした〈点より〉、〈線より〉シリーズだ。
〈点より〉の初期作品は、1本の筆を青の岩絵具に浸し、白地のカンヴァスの上に左端から右へと点をほぼ等間隔で連ねた列を上から下へと規則的に繰り返して描いたもので、繰り返されるうちに点はかすれている。他の作品では1本の列の中で何度か筆に絵具を付け直し、濃淡の変化がそれぞれに異なった長さで繰り返され、全体としては規則的な変化をランダムに配置する“単純にして複雑”な効果が生じているものもある。〈線より〉も同様の方法で縦の線を上から下へと引いたもので、規則正しく引かれる線は、次第に薄らいでいつの間にか消える。反復とはいえ、そのひとつひとつの点、線は他にかえがたい唯一無二の行為の現出でもある。呼吸と行為による時間の経過を示す、このシステマティックな仕事は10年ほど持続し展開された。

展示風景より、〈点より〉シリーズ

展示風景より、〈線より〉シリーズ
1980年代に入り、李の絵画のシステムが崩れ、80年代半ばには規則的な反復を退け、画面に短いストロークを散在させた〈風より〉〈風と共に〉シリーズにより、縦横をめぐる混沌とした画面が展開されるようになる。画面はいっそうダイナミックに湧き立ち、素早いストロークが密集したり、飛散したりしながら、躍動する空間を形成していく。 そして80年代終わり頃から、画面がだんだんいくつかのストロークに整理されつつ、描かぬ空白が目立つようになる。 1990年代から始まる〈照応〉のシリーズでは、ストロークは短く簡潔なものとなり、水平・垂直方向に限定された。
それらは互いに反発したり、応答したりしながら緊密な関係を切り結び、カンヴァスの空白と対峙する。制作の原理が、時間性の強い反復から空間におけるバランスと関係の力学へと変化したことで、絵画はカンヴァスの枠を越えて外部の空間とも響きあう、開かれた場となっていくこととなる。李は2000年に刊行された「余白の芸術」において、「呼吸を整え身体でリズムを感じながら、カンヴァスの何処かに筆をおろす。するとその一画に対応するかのようなあるところへ、おのずと筆を運びたくなる。するとまた別な抜き差しならぬ位置が筆を呼ぶ。まるで碁を打つようにして、緊張した場面が形成されてゆく」と記している。
2000年代になると、李の筆はいっそう切りつめられ、描くことを極端に限定し、描かぬ空白との対応を積極的に試みるようにもなる。カンヴァスの一部に刺激的なストロークを描くことによって、筆触と余白の反響は空間的な絵画へと変貌を成し遂げた。〈対話〉のシリーズは、李の絵画が従来に増して身体を介した空間的な経験をもたらすものとなりつつあることを示し、しばしばカンヴァスにではなく壁面にも筆を入れる李は、本展において国立新美術館の展示室の壁面に《対話―ウォールペインティング》を描いた。
ここまで紹介してきたとおり、本展では李禹煥の過去の作品の再解釈や、本展に合わせた作品の配置、空間づくりなど、李のこれまでと新境地(外部や他者との関係の中での無限)を余すことなく感じとれる展示となっている。この機会にぜひ会場に足を運んでみてはいかがだろうか。

展示風景より、〈風より〉〈風と共に〉シリーズ

展示風景より、〈対話〉シリーズ

《対話─ウォールペインティング》(2022)作家蔵
文=鈴木隆一
写真=新井まる
【アーティスト プロフィール】
李禹煥(Lee Ufan)
1936年、韓国慶尚南道生まれ。ソウル大学校美術大学入学後の1956年に来日し、その後、日本大学文学部で哲学を学ぶ。1960年代末から始まった「もの派」を牽引。近年ではグッゲンハイム美術館(ニューヨーク、アメリカ合衆国、2011年)、ヴェルサイユ宮殿(ヴェルサイユ、フランス、2014年)、ポンピドゥー・センター・メッス(メッス、フランス、2019年)で個展を開催するなど、ますます活躍の場を広げている。国内では、2010年に香川県直島町に安藤忠雄設計の李禹煥美術館が開館している。
【展覧会情報】
国立新美術館開館15周年記念 李禹煥
会期|2022年8月10日〜11月7日
会場|国立新美術館 企画展示室1E
住所|東京都港区六本木7-22-2
電話番号|050-5541-8600(ハローダイヤル)
開館時間|10:00~18:00(金土〜20:00) 火曜休館 ※入場は閉館の30分前まで
料金|一般 1700円 / 大学生 1200円 / 高校生 800円
巡回
兵庫県立美術館:2022年12月13日〜2023年2月12日
※各会場で一部展示作品が異なる
トップ画像:《関係項―アーチ》(2014/2022) 作家蔵