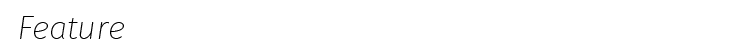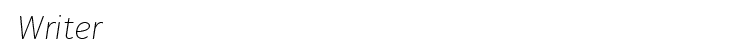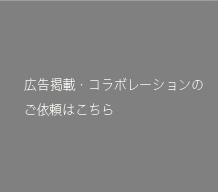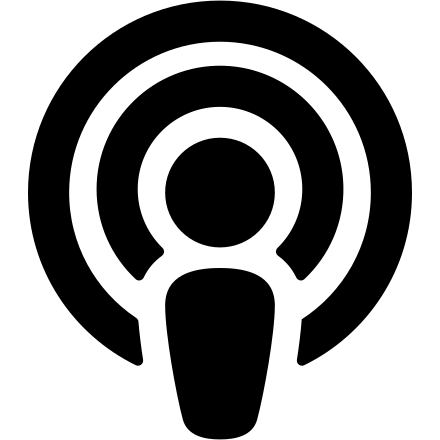彼女の秘密はパリにある!ボストン美術館「パリジェンヌ展」時代を映す女性たち
みなさんは、パリジェンヌという言葉から、どんな女性をイメージしますか?
往年のフランス映画を賑わせた女優、ブリジット・バルドーやカトリーヌ・ドヌーヴ?
フレンチ・ポップの歌い手、ジェーン・バーキンやフランス・ギャル?
それとも、モード界で活躍するエマニュエル・アルトやイネス・ド・ラ・フレサンジュ?
エンターテイメント界でもファッション界でも、今昔、愛され続けているのはパリジェンヌですね。
パリを舞台に活躍する彼女たちは、それぞれが強烈な個性を持っていて、なかなか一言では表現しきれません。「パリジェンヌとは何者なのか?」そんな疑問の答えを見つけられる展覧会が、世田谷美術館で開催中です。
ボストン美術館「パリジェンヌ展」時代を映す女性たちは、私たちを惹きつけてやまない、パリジェンヌという存在にスポットを当てた企画展です。
ボストン美術館が所蔵する18世紀から20世紀まで、250年間のパリに関連する約120点の作品を通し「憧れるのは何故?」というキーワードと共にパリジェンヌの本質を探ります。

ボストン出身者には、フランスに惹かれた人が多く存在し、ボストン市民から美術館に寄贈された19世紀フランス絵画や資料のコレクションの一部が来日しています。
キュレーターは、ボストン美術館のケイティ・ハンソン氏。
5章立ての展覧会の内容に沿って、お勧め作品をご紹介していきましょう。
第1章 パリという舞台―邸宅と劇場にみる18世紀のエレガンス
本展は、華やかなサロン文化から幕を開けます。
ルイ14世の治世が終わり、宮廷ヴェルサイユに代わってパリに文化の中心地が移った時代、思想家や芸術家などの文化的エリートたちは、個人宅で開催される「サロン」という集まりに参加することで、交友関係を広げていました。
サロンの主催者の多くは、その家の女主人でした。センスよく整えた調度品のある部屋で、知性に富む会話と茶菓子で客をもてなすという重要な役割を女性たちが担っていたのです。
サロンに華を添えるドレス

《ドレス(3つのパーツからなる)》1770年頃
客人を迎えるために、ドレスは豪華で優美なデザインが好まれました。こちらのドレスはリボン、花かご、小紋模様が織り出された、リヨン製のシルク素材で作られています。胸元や袖口のフリルが、一挙一動をよりエレガントに見せていたのでしょう。
スカート部分は、パニエと呼ばれる籠素材の下着を着用することによってボリュームを持たせていました。上半身には、ウエストを細く、バストを豊かに見せるためにコルセット(補正下着)を身につけていたこの時代。人前で美しい姿でいるには、並々ならぬ我慢も必要でした。
おもてなしはエキゾチックに
少し風変わりな、こちらのティーセット。パリ製の銀器に加え、日本の有田磁器に銀を組み合わせた砂糖入れ、柿右衛門のティーボウルとソーサーが含まれています。ルイ王政の時代から、異国趣味として日本や中国の陶磁器が宮廷で好まれていました。物珍しい異国風の工芸品は、サロンでの会話に一役買っていたのですね。

伝マルタン・ベルト 《ティーセット(箱付)》1728-29年
パリは流行の発信地
既にこの時代、パリの最新の流行を伝えるファッション雑誌が存在していました。
『ギャルリー・デ・モード・エ・コスチューム・フランセ』はヨーロッパ中に広がり、瞬く間にフランスがファッションの中心地として認識されるようになりました。

『ギャルリー・デ・モード・エ・コスチューム・フランセ』1776年以降のフランスの流行の髪型6より 1776年
ヘアスタイルの見本のページ。帆船が後頭部に乗ったヘアスタイルや、羽根で飾り立てたスタイルは、マリー・アントワネットの肖像でもお馴染みですが、やはり奇抜です。しかし、センセーショナルなスタイルを生み出してこそ、ファッションリーダー。一目見たら忘れられないインパクトが、世界で噂になり、パリジェンヌたちの知名度アップに貢献したのでしょう。
第2章 日々の生活―家庭と仕事、女性の役割
第1章の華やかなサロンの世界とは異なり、第2章では労働階級と中流階級にスポットを当てた風俗画を紹介しています。
フランス革命前夜のナポレオンの統治下では「理想の家庭像」が絵画のモチーフとして流行しました。良い母親像の模範を示すようなフラゴナールの油彩画や、流行の衣服に身を包む母親と娘を描いたファッション誌が、それを伝えています。
未亡人の肖像

トマ・クチュール 《未亡人》1840年
そんな優等生のような女性像が並ぶ中で、異色を放つ作品が上の一枚です。
《未亡人》は、夫に先立たれた女性の肖像画です。複雑な表情が、喪に服した黒いドレスと共に陰鬱な空気を伝えています。当時、戦争を機に、未亡人を守るための法律が制定されましたが、経済的な困窮から彼女たちを救うことは難しかったそうです。悲しみというよりは、どこか不服そうにも見える女性の表情は、不幸な現状への苛立ちが感じられます。まだ年も若い彼女の余生がどうなったのか、気になります。
強気な女性は笑われる?
一般庶民の間にも「女性は家庭を守るべき」という風潮がまだ強かった頃、男性社会で職を得ようとする女性たちは批判の対象になりました。
オノレ・ドーミエによる〈青鞜派〉シリーズは風刺新聞『シャリヴァリ』に連載されました。タイトルの「青踏派」という言葉は、元々は「イギリスで青い毛糸のストッキングを身につけた知識人」を指す言葉。フランスでは「サロンに集まる女性」を指す言葉として用いられてきましたが、ドーミエの時代には「文学、学問に野心を持ちつつも、外見がだらしない女性」を軽蔑するための名称に転じました。

オノレ・ドーミエ《〈青鞜派〉第28図(『シャリヴァリ』1844年5月23日)》1844年 Bequest of William Perkins Babcock 00.1971.28
絵の下に添えられた文の訳:
―私ほどの女性に…ボタン付けをしてくれですって?…ちょっと頭おかしくなったんじゃないの!…
―なんだと!…キュロットをはくだけではもの足りず…そいつを俺の頭めがけて投げつけるというわけだな!…
思わず、笑ってしまうこの夫婦のやりとり。当時、キュロットは男性のための衣服でしたが、女性解放を唱えた女流作家・ジョルジュ・サンドは、時に男装をして周囲を驚かせていました。キュロットは男性に対抗する女性の象徴的アイテムだったのかもしれません。
日本でも物議を醸した新聞でもお馴染みのフランスの風刺精神。社会に進出しようとする女性たちは好意的に受け入れられず、こんな風に嘲笑されていました。男性たちは、パワフルすぎる女性たちに焦ってしまったのでしょうか?
第3章 「パリジェンヌ」の確立―憧れのスタイル
パリは、ナポレオン3世の第二帝政時代に、今日に見られるオスマン様式の街並みへと大改装されました。都市文化が成熟しつつあった時代に「パリジェンヌ」を論じた本も出版されました。パリはファッションの都となり、人々は雑誌や広告に溢れる流行を求めて、百貨店やデザイナーの元へと集まりました。
ウジェニー皇妃は、いつもお手本
パリ社交界の最高位にいた女性たちは、ナポレオン皇妃のウジェニーのスタイルを模範としました。皇妃は今で言う、インフルエンサーだったのです。
パリで多くの時を過ごしたポーランド貴族の夫人の肖像です。フランス風の肖像画の製作を、皇妃お気に入りの画家、フランツ・クサーヴァー・ヴィンターハルターに依頼しました。

フランツ・クサーヴァー・ヴィンターハルター 《ヴィンチェスラヴァ・バーチェスカ、ユニヤヴィッチ夫人》1860年
既婚女性が人前では髪を束ねるのが常識でしたが、こちらは室内に飾る肖像画だったためか、ほどいた髪の姿で、どこか親密な空気が漂っています。たっぷりとした白いシルクのドレスと、ウェーブのかかった髪が柔らかな印象を作り上げています。
アメリカでも流行したイギリス人デザイナー・ウォルトのドレス
ライラック色のドレスは、一世風靡したファッションデザイナー、シャルル・フレデリック・ウォルトによるものです。皇妃のフォーマルウエアの専属デザイナーとして信頼を得ました。
ウォルトはイギリスの仕立て屋で訓練後、パリで販売員として働いていた際に、服のコーディネートの重要性に気づき、独自のビジネスで成功を収めました。アメリカでも人気を博し、上流階級の女性からの注文を多く受けました。

シャルル・フレデリック・ウォルト ウォルト社のためのデザイン 《ドレス(5つのパーツからなる)》1870年頃
ドレスには彼の名を刺繍したラベルが付けられています。爆発的な人気ゆえ、模倣品が大量に出回り、本物を区別するために考案されました。現代も続く、ブランドビジネスの萌芽と言えます。19世紀に発明されたアニリン染料による、鮮やかな紫色の目新しさは、顧客の女性達の欲望を掻き立てたことでしょう。
フランスの面影を追い求めて
フランスの流行のドレスにおさげ髪姿のアメリカ人の少女の姿。ウィリアム・モリス・ハントはフランスに滞在した10年の間に、ある農家の女性像を描きました。その15年後にアメリカに戻った彼は、アップデートしたアメリカ版の本作を描きました。

ウィリアム・モリス・ハント 《マルグリット》1870年
ヘアスタイルは、同展示室内のファッションプレートに似た例があります。両作のタイトルは《マルグリット》。フランス語でヒナギクの意味で、少女の手元の花として描かれています。一度パリで暮らした者は、いつまでもパリへのイメージが心に住み着いて離れない、そんなことを語るような一枚です。
第4章 芸術をとりまく環境―制作者、モデル、ミューズ
19世紀後半、未だパリの国立美術学校は保守的でした。女性たちには解剖学と美術史の講義のみ開講され、人体のデッサンが許可されたのは1900年以降でした。そんな状況下でも、近代絵画の印象派などの新興グループは女性画家たちの活躍に寛容でした。
アメリカからパリに渡った女性画家・カサット
メアリー・カサットはアメリカで絵画を学び、パリに移住後に印象派画家たちと親交を深め、成功を収めた女性画家です。

メアリー・スティーヴンソン・カサット 《縞模様のソファで読書するダフィー夫人》1876年
絵画を実際に見られる美術館やギャラリーが多くあるパリで暮らしたいと考えたカサットは渡仏し、巨匠の画家の下で修行しました。画家で、マネの弟の妻、モデルも多く務めたベルト・モリゾとも仲が良く、一時はアメリカに帰るも、パリに戻り生涯を終えました。
アメリカ人の富裕層の女性が読書する姿を捉えた油彩画は、フランスのロココ時代の画家、フラゴナールを思い起こさせる柔らかなタッチと幸福感のある色合いで描かれています。カサットのフランス絵画への憧れが透けて見える一枚です。
ドガが捉えたルーヴル美術館の女性たち
ドガはルーヴル美術館で絵画を鑑賞する、二人の女性像を残しています。黒いドレスに身を包んだ女性たちは、メモを片手に作品について話し合っているようです。頻繁に美術館に足を運んでいたカサットと、その姉がモデルと見なされていました。

エドガー・ドガ 《美術館にて》1879−90年頃
男性を伴わない女性が街を歩くことが、まだ少なかった時代。自らの意思で芸術制作に挑み、古典絵画から学ぼうとしている女性たちの姿勢が、ドガにインスピレーションを与えたのかもしれません。
芸術の都であったパリでは、世界中からアーティストが集い、美術学校以外の場でもモデルが必要とされていました。画家たちは各々、自分の気に入ったモデルを見つけ、時に何度も同じ女性を描きました。創作力の源となる女性たちは「ミューズ」と呼ばれ、彼らの芸術家人生を大きく左右する存在でした。
マネのミューズ・ムーラン

エドゥアール・マネ 《街の歌い手》1862年頃
マネの《街の歌い手》のモデル、ヴィクトリーヌ・ムーランもその一人。マネの代表作《草上の昼食》、《オランピア》を含む多数の作品のモデルを務めた女性です。
サクランボを口に運びながらギターを片手に居酒屋から出てくる彼女は、冷静な視線を遠くへ投げかけています。誰にも頼らずに生きていけるような、自立した女性像が想像できます。
大きめのキャンバスに描かれ、モデルが歩いてきそうなリアリスティックな作品です。今回は70年ぶりにキャンバスの表面の劣化したニスを修復、色鮮やかに蘇った姿での来日となりました。
第5章 モダン・シーン―舞台、街角、スタジオ
ファッションの都として未だ活気のあったパリ。アールデコの時代には、人気のイラストレーターたちによる、手彩色によるポショワールと呼ばれる版画が、最新のモードを伝えていました。

ゲアダ・ヴィーイナ 《スコットランドシルクのベスト、ねずみ色の綿の厚手クレープのスカート『ジュルナル・デ・ダム・エ・デ・モード』より、プレート170》1914年
デンマーク出身のゲアダ・ヴィーイナによるイラストレーション。ゲアダのパートナー、アイナー・ヴィーイナは、女性の衣服を身につけ、頻繁にモデルを務めました。女装がきっかけとなり、自分の心的な性に気づいたアイナーは世界初の女性性転換手術をし、リリー・エルベとなりました。カップルのストーリーは『リリーのすべて』(監督トム・フーパー、2016年公開)で映画化され、ご存知の方も多いのでは?
ブルジョワ階級の女性の必需品だった帽子と日傘を手にしたモデルは、濃いめのメイキャップに最新のスリムなドレスでくつろ寛いだポーズで座っています。足元には、ちょっと意地悪そうな顔の猫が戯れています。
モンパルナスのミューズ・キキ
20世紀になり大戦の狭間でパリの娯楽は広がっていきました。キャバレーや、ダンスホールで女性のパフォーマーが煌びやかな衣装で踊り、夜の街を明るく照らしました。

ブラッサイ(ギューラ・ハラス)《モンパルナスのキャバレーで歌うキキ》1933年
こちらは、「モンパルナスの女王」と呼ばれた女性キキ(本名アリス・プラン)がキャバレーで歌う姿を、写真家のブラッサイが捉えた作品です。自信たっぷりに歌うキキと、彼女を見つめる人たちが、当時のパリの夜の空気を伝えます。
キキは若い頃に田舎から出てきて、パリで歌手になりました。持ち前の明るく、お祭り好きな性格から、モディリアーニやキスリングなどエコール・ド・パリの画家たちに慕われ、モデルとして数々の絵画に登場しています。藤田嗣治の親しい友人でもありました。マン・レイと結婚をし、アメリカでも興行するなど、モンパルナスの芸術家に愛されたパリジェンヌです。
時代を語る、3着のプティ・ローブ・ノワール(黒のドレス)
流行を牽引するパリ・コレクションは、今も世間の注目の的。パリで活躍した3人のデザイナーによる黒のドレスからは、20年ごとの流行の変遷を見ることができます。

前:ジャン・パトゥ パトゥ社のためのデザイン ドレス 1925−28年
コルセットの無しのローウエストの真っ直ぐなラインが1920年代に流行しました。ショートカットで、締め付けのない自由な服を着た若い女性たちは「フラッパー」と呼ばれ、大戦後の狭間を享楽的に生きたのです。
中:クリストバル・バレンシアガ ツーピースのカクテルドレス 1949年
ウエストを絞った逆三角形型のシルエットは、クリスチャン・ディオールが1947年に発表したニュールックと共通しています。戦中のストイックなファッションを経て、女性らしさを強調したクラシックなスタイルは、戦後喜んで迎えられました。
後:ピエール・カルダン ドレス 1965年頃
膝上のミニ丈のスカートはロンドンで誕生したと言われていますが、1960年代に始まった女性解放運動・ウーマンリブとも関係があります。ビニールを使ったデザインは当時目新しく、コスモコール(宇宙的)と呼ばれ、カルダンの名を世界に広めたコレクションです。
海外に行くことが滅多にできなかった時代、パリで活躍するデザイナーたちの創作源は、身近なパリジェンヌだったことを考えると、数々のファッションアイコンが生まれたことにも納得ですね。
本展を通して考える。「憧れるのは、なぜ?」
パリジェンヌの250年を巡り、国籍も身分もまるで異なる、それぞれが強い個性を放つ女性像と出会い、「憧れるのは、なぜ?」という最初の問いの答えが見えてきました。
私がパリジェンヌたちに憧れるのは、「どんな時代や生い立ちであっても、自分のセンスに自信をもって、前進しているから」でした。
今日ほど女性の権利が認められず、自由がなかった時代にも、パワフルに生きるパリジェンヌの姿には勇気をもらえることでしょう。
バラエティに富んだ展示品の数々は、じっくりと鑑賞したくなる作品ばかり。美術史的な面白さだけではな く、ジェンダー論や服飾史、都市文化史という視点からも、楽しめると思います。
ぜひ、パリジェンヌの多彩な魅力を探してみてくださいね。
音声ガイド&グッズ情報
音声ガイドは、パリ在住歴の長い中村江里子さんと声優の梅原裕一郎さんがナレーションを担当しています。フランスの音楽も挿入されていて、往年のパリの雰囲気を感じながら鑑賞することができます。

記者会見時に《街の歌い手》の前で微笑む中村江里子さん
グッズのコーナーでは、本展オリジナルのミラーを見つけました。片面がミラーになっていて、出してすぐに見られるので、携帯に便利なデザインです。

人気ブランドMUVEIL(ミュベール)と本展の限定コラボレーションのキュートなグランマチャームは、2月28日まで美術館ショップもしくはパルコのウェブサイトで予約を受付中です。他にも人気ブランドの本展限定グッズが販売中です。
パルコMEETSCALストア http://www.meetscal.parco.jp

写真:新井まる、Foujii Ryoco
画像提供:世田谷美術館
文:Foujii Ryoco
参考文献:ボストン美術館「パリジェンヌ展」時代を映す女性たち カタログ
【展覧会概要】
ボストン美術館「パリジェンヌ展」時代を映す女性たち
会期:開催中~4月1日(日)
会場:世田谷美術館
住所:〒157-0075 東京都世田谷区砧公園1-2
Tel:03-5777-8600(ハローダイヤル)
開館時間:10:00-18:00 (入場は17:30まで)
休館日 月曜日 ※2月12日(月・振替休日)は開館、翌13日(火)は休館
観覧料(税込)一般:1,500(1,300)円、65歳以上:1,200(1,000)円、大高生:900(700)円、中小生:500(300)円 ※( )内は団体(20名以上)
※障害者の方は500円(介助の方1名まで無料)、大高中小生の障害者の方は無料
※リピーター割引/会期中、本展有料チケットの半券をご提示いただくと、2回目以降は団体料金でご覧いただけます
展覧会公式HP:http://paris2017-18.jp/
世田谷美術館公式HP:https://www.setagayaartmuseum.or.jp
【パリジェンヌ展に関する他の記事はこちら!】
学芸員さん、教えて!いつの時代も世界の憧れ!パリジェンヌの魅力
250年分のパリジェンヌのヒミツがわかる!「パリジェンヌ展」【先取りおすすめアート】
【Foujii Ryocoの他の記事はこちら♪】
女性の美的瞬間に迫る『フランク ホーヴァット写真展 Un moment d’une femme 』
足を止めて、身体で見て、言葉にして 石内 都 「肌理(きめ)と写真」展
庭園美術館が問いかける現代「装飾は流転する 今と向きあう7つの方法」