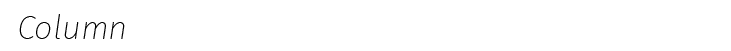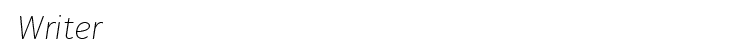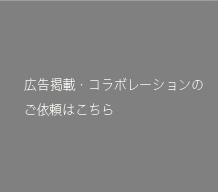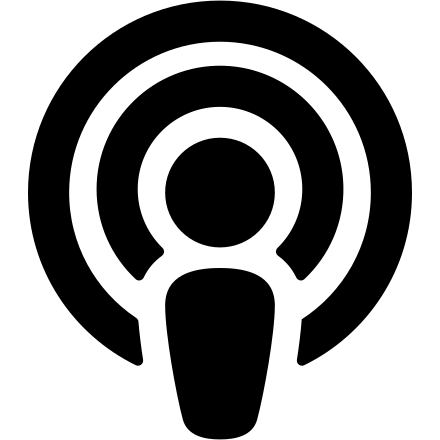肖像画と女心 vol.1 「こんな顔じゃない!」
現代なら写真、そして昔なら肖像画―――人は、これらを通して自分の姿を形として残してきました。
その根底にある目的は「生きている証」を残すこと。
そして、「綺麗に描いて(撮って)もらいたい」という願いもまた、共通していると言えるのではないでしょうか。
美術館に展示されている肖像画の中でも、女性がモデルになっている作品は、ファッションや髪型など、見ているだけで心浮き立つ者が少なくありません。
そのような作品にまつわるエピソードを紐解けば、現れるのは、今ここに生きている私たちと変わらない等身大の女性たちの姿です。
ファッションやポーズへのこだわり。
できあがった作品を見て、「これが私?」と感嘆したり、逆に「私はこんな顔じゃない」と怒ったり。
このシリーズでは、女性の肖像画と、それをめぐる女性たちの「人間ドラマ」をご紹介しましょう。
①花魁・四代目小稲の場合
最初のヒロインは、幕末から明治にかけて生きた花魁・四代目小稲です。
花魁といえば、江戸時代・新吉原の遊女の中でも最高ランクに位置する女性たちのこと。
胸の前で太鼓帯を締め、頭には何本もの簪を刺した華やかな姿、また行列を組んで街を練り歩く「花魁道中」のイメージは、漫画や映画などでもなじみ深いものでしょう。
浮世絵でも、しばしば美人画のモデルとして取り上げられています。

喜多川歌麿、<青楼七小町 玉屋内花紫>、1790年、メトロポリタン美術館

喜多川歌麿、<青楼十二刻 申の刻>、1794年、シカゴ美術館
稲本楼の四代目・小稲も、「当代一」と名高い一人でした。
幕末に活躍した隻腕の剣士・伊庭八郎の恋人で、彼が幕府軍の一員として最後まで戦うべく、函館へと向かう際には、旅費として50両を用意した人物です。(彼は半年後に函館戦争で戦死し、二人は二度と会う事はありませんでした)
そんな彼女は、一体、どんな容姿の女性だったのでしょう?
明治時代に入ってから、描かれた彼女の肖像画が残っています。

高橋由一、<花魁>、1872年、東京芸術大学
描いたのは、日本初の洋画家・高橋由一。美術の教科書によく載っている<鮭>の絵の作者です。
日本人として初めて西洋の油彩技法を本格的に学んだ彼は、「見えたままを描き出す」ことを売りにしており、この<花魁>もその例に漏れませんでした。
しかし、「見えたまま」「ありのまま」を正直に描き出すことは、必ずしも最善とは限りません。
実際に彼の絵を見た小稲は、泣いて怒ります。
「私はこんな年増じゃないっ!!」
当時、遊女を描いた絵、と言えば、ヨーロッパの肖像画のように目の前のモデルの姿をそのまま(細部に多少の修正は加えるにせよ)写すのではなく、上にあげた歌麿の作品のように、デフォルメされた美人画でした。
小稲さんも、自分の絵を描いてもらう、と聞いた時に思い描いたのも、歌麿風の美人画でした。
彼女のショックはどれほど大きかったでしょう。
実は、そもそも上の<花魁>が制作されたのは、洋風化が進む中で消えていこうとしている文化を「記録」として残すという目的がありました。
その点から考えると、色彩も形も、「見えたままを描く」高橋由一の技法は、当時まだモノクロだった写真よりも、その目的には適したものでした。
ですが、そのような事情を差し引いたとしても、「これが現実の貴女です」「見えたままを描きました」とこの<花魁>のような絵を差し出されたら、…貴方は、どう思いますか?
②マントヴァ侯妃イザベッラ・デステの場合
次にご紹介するのは、ルネサンス期のイタリアから、マントヴァ侯妃イザベッラ・デステ(1474~1539)。
一説には、あのレオナルド・ダ・ヴィンチの<モナ・リザ>のモデルとも言われている女性です。
彼女は美しいだけではなく、教養や政治的な才能も持ち、当時のイタリア情勢で政治的・外交的手腕を発揮してマントヴァ侯国を守りぬきます。また、夫の死後は、息子を支え、マントヴァをワンランク上の公国へと昇格させることに尽力しました。
その一方で芸術を庇護し、ファッションリーダーとしても、イタリア各国やフランスの宮廷に影響を与えています。
これらの事績から、同時代人たちからも「最高の女性」「世界一のファーストレディ」と評価された、まさに「女傑」という言葉がふさわしい女性です。
そんな自分の肖像画を、当代最高の画家に描いてもらいたい。
そう思ったイザベッラは、あらゆる画家たちに声をかけます。が、なかなかOKしてくれる人が見つかりません。(レオナルドには、デッサンを一枚描かれただけであとはうやむやにされました)
どうにか、ヴェネツィア派の大家ティツィアーノに描いてもらえることになります。
当時のイザベッラは50代。
最初は、見たままの姿を描いてもらったのですが、気に入りません。
年を取った自分の姿が、絵として永遠に残り続けることに、プライドの高い彼女は、我慢ができなかったのでしょう。
絵の中だけでも、かつての一番美しく輝いていた頃の自分に戻りたい。
そんな思いもあったかもしれません。
彼女は、若いころの肖像画を渡し、「これを参考にして描き直すように」と命じます。
なかなか無茶な注文ですが、ティツィアーノも、イタリア諸国の君主や教皇、神聖ローマ皇帝と、当時のヨーロッパの名だたるセレブ達を相手に仕事をこなしてきた男です。内心はどうあれ、承諾しました。
そして描きあがったのがこちらです。

ティツィアーノ・ヴィチェリオ、<イザベッラ・デステの肖像>、1534~6年、ウィーン美術史美術館
凛とこちらを見据える眼差しが印象的ですね。
肩から斜めにかけた毛皮もオシャレです。また、頭にかぶったターバン風の帽子は、彼女自身がデザインし、マントヴァの名品となったアイテムです。
美しさ、賢さ、強さ、そしてファッションセンス…彼女を構成するあらゆる要素が詰め込まれています。
ここまで描いてもらえば、文句は出ないでしょう。
イザベッラも今度はちゃんと受け取りました。が、一方で手紙の中でこう漏らしています。
「…私は、こんなに美しくはなかった」
なかなか複雑ですね。
思う通りの姿に描いてもらえず、泣いて怒った小稲。
一方、なまじ見栄を張ったばかりに手痛いしっぺ返しを食らったイザベッラ。
「どうせなら、美しく描いて欲しい」
「美しい姿を残したい」
そんな彼女たちの思いは、現代の私たちにも共通するものでしょう。
ちなみに、ティツィアーノは、上の絵の少し後には、ウルビーノでイザベッラの娘エレオノーラの肖像画も手掛けています。

ティツィアーノ・ヴィチェリオ、<ウルビーノ公妃エレオノーラ・ゴンザーガの肖像>、1537年頃、ウフィツィ美術館
こちらは母と違い、50前という年齢相応の姿で描かれています。
顔立ちからは、ゆったりと落ち着いた人柄や気品、知性が感じられ、『婦人公論』など、雑誌のインタビュー記事や、教養番組のコメンテーターとして登場しそうな印象です。
背伸びしすぎない、自然で、内側から輝いているかのような姿―――「ありのままの彼女自身」と言っても良いのではないでしょうか。(こんな風に描いてもらえたら、素敵ですね)
50代の自分を描いた絵は気に入らずに突き返したイザベッラでしたが、一体どんな絵だったのでしょうか。
<参考>
①喜多川歌麿、<青楼七小町 玉屋内花紫>、1790年、メトロポリタン美術館 (パブリックドメイン)
出典:https://www.metmuseum.org/art/collection/search/55138
②喜多川歌麿、<青楼十二刻 申の刻>、1794年、シカゴ美術館 (パブリックドメイン)
③高橋由一、<花魁>、1872年、東京芸術大学 (パブリックドメイン)
④ティツィアーノ・ヴィチェリオ、<イザベッラ・デステの肖像>、1534~6年、ウィーン美術史美術館 (パブリックドメイン)
⑤ティツィアーノ・ヴィチェリオ、<ウルビーノ公妃エレオノーラ・ゴンザーガの肖像>、1537年頃、ウフィツィ美術館
出典: