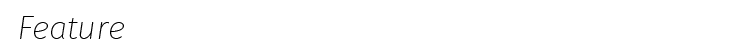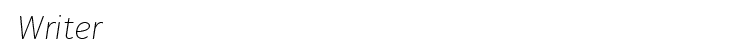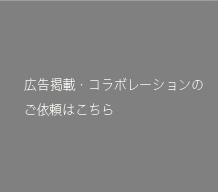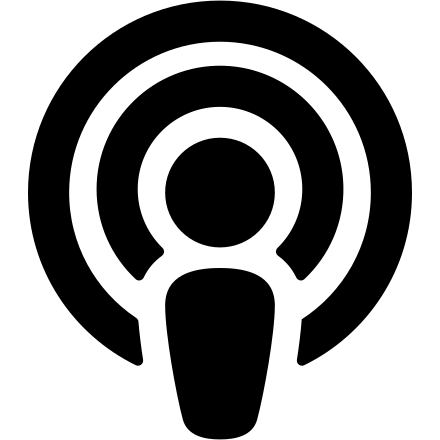肖像画と女心 vol.2「女王エリザベスのイメージ戦略」
人はなぜ、肖像画を描かせるのでしょうか。
一つは、今生きている自分を記録するため。
直近の自分の姿を写した一枚があれば、同時代に生きている、会ったことのない(また会う機会のない)人にも、自分がどんな人間かを知ってもらえます。
「お見合い」写真としての利用は、その活用例でしょう。
また、描かせる際には、多少の修正を加えたり、小道具や衣装に工夫を凝らすことで、相手に見せる「イメージ」をコントロールすることもできます。
こうした肖像画による「プロパガンダ」の力を、大いに利用した一人が、16世紀イギリスに君臨し、黄金時代を築いた「処女王(ヴァージン・クイーン)」エリザベス1世です。
彼女の生前に描かれた肖像画は数十枚以上、それらには、「特別で神聖な存在」としてのイメージ作りのためあらゆる工夫が散りばめられています。
その工夫とは?
そもそも、なぜ「処女王」のイメージにこだわる必要があったのか。
今回は、現在、上野の森美術館で開催されている「KING&QUEEN」展に寄せ、その展示作品と共に、女王のイメージ戦略の物語、追って見ましょう。

《エリザベス1世(アルマダの肖像画)》 Queen Elizabeth I (‘The Armada Portrait’) by Unidentified artist (c.1588) ©National Portrait Gallery, London
①エリザベス1世、女王への道
エリザベス1世は、1533年、イングランド国王ヘンリー8世の次女として生まれました。
しかし、2歳の時に、母アン・ブーリンが姦通罪で処刑され、エリザベスも「王女」から一転、「庶子」に落とされます。

《ヘンリー8世》 King Henry VIII by Unidentified artist, after Hans Holbein the Younger, Probably 17th century(1536) ©National Portrait Gallery, London

《アン・ブーリン》 Anne Boleyn by Unidentified artist, Late 16th century(c.1533-36) ©National Portrait Gallery, London
後に王位継承権は回復され、姉の死を受けて25歳で王位につきますが、一時的にでも「庶子」だったこと、そして「罪人の娘」である、という事実は、彼女につきまとい続けます。
敵にとっては格好の攻撃材料でしたし、彼女自身にとっても大きなコンプレックスとなっていたのです。
王女として生まれながら、庶子に落とされ、時に「罪人の娘」として扱われながら成長したエリザベスにとって、王冠を手にできたことは、まさに奇跡でした。
手放したくない、と思うのは自然なこと。
そう、たとえ、一個人として、一人の女性としての幸福を犠牲にしたとしても・・・。
女王になったばかりの頃、エリザベスには、心を寄せる相手がいました。
幼馴染みでもあった側近ロバート・ダドリーです。
彼に夢中で、外国からの縁談にも見向きをしなかったと言われるほどでした。
が、国のトップである自分が結婚すれば、イングランドの政治に何らかの波紋をもたらさずには済みません。
国内の貴族の誰かを選べば、反発する者が出ます。外国の王族と結婚すれば、相手はイングランドの政治に介入してくるのは明白です。
悩みに悩んだ末、彼女は生涯結婚せず、独身を通す道を選びます。
女性としての幸せを諦め、王として生きることを選んだのです。
そして、自らを「国家(イングランド)と結婚した処女王」として、神聖化、神格化していくことに努めました。
そのイメージを広め、定着させるためのツールの一つが、肖像画でした。


②女王のイメージ戦略~肖像画に仕込まれた演出技法
エリザベス1世の肖像画、と言われて、思い浮かぶのは、白塗りののっぺりした顔と、そして刺繍や宝石を散りばめたきらびやかな衣装でしょう。
その姿は、時に、生身の人間の女性というよりも、アンドロイドめいて見えます。
それらの肖像画には、普通の人間とは一線を画す特別な存在、女神のような存在としての「処女王」を演出するための工夫が凝らされています。
例えば、アクセサリーに着目してみましょう。

《エリザベス1世(アルマダの肖像画)》 Queen Elizabeth I (‘The Armada Portrait’) by Unidentified artist (c.1588) ©National Portrait Gallery, London
エリザベスのどの肖像画でも、必ず身に着けているのが、真珠!
この〈アルマダ・ポートレート〉 でも、首飾りにするのはもちろん、ドレスにも、髪にもいくつも飾っています。
エリザベス自身、真珠が好きだったのもありますが、量が半端ではありませんよね・・・。
実は、真珠の石言葉は「純潔」。
それを踏まえると、「処女王」エリザベスにとって、これほどふさわしい宝石はないでしょう。
同じく「純潔」を象徴するアイテムとして、羽根や篩を手にしていることもあります。
言ってしまえば、これらは、エリザベスを象徴する「アトリビュート(持物)」として、位置づけられているのです。

(参考図版)作者不詳《女王エリザベス1世》1575年頃 ナショナル・ポートレート・ギャラリー所蔵(KING&QUEEN展には出品されていません)

(参考図版)クエンテイン・マサイス《エリザベス1世(篩の肖像画)》1583年 シエナ国立絵画館(KING&QUEEN展には出品されていません)
工夫の二つ目は、陰影をつけさせないこと。
陰影をつけて描けば、モデルの姿に立体感が生まれ、より生き生きと写実的に描き出すことができます。
では、逆に全く陰影をつけなかったら?

(参考図版)ニコラス・ヒリアード《エリザベス1世(フェニックス・ポートレート)》1575~76年頃 テート・ブリテン(ナショナル・ポートレート・ギャラリーより貸出)(KING&QUEEN展には出品されていません)
このように、平板で硬く、のっぺりした印象になりますね。日本の浮世絵に近いでしょうか?
生きた人間の女性、とはちょっと見えない…ですが、それこそがエリザベスの狙いでした。
普通の人間とは一線を画した、女神のような存在として、自分を印象づけようとしたのです。
肖像画を描かせる際、アトリエではなく、陽のあたる戸外でポーズを取った、という記録もあります。
直接会ったことのない人にも、自分の外見イメージを伝えることができる、肖像画の力をエリザベスはよく知っていました。
1569年からは肖像画に検閲を行い、皺は絶対描かせず、肌は白く、常に若々しく描かせることを絶対としていました。
実際に、60代後半の頃に描かれた一枚を見てみましょう。

(参考図版)アイザック・オリヴァー《エリザベス1世、虹の肖像画》ハットフィールド・ハウス 1600~2年(KING&QUEEN展には出品されていません)
髪や王冠、首や手首にお馴染みの真珠。
左袖の蛇は「知恵」を、そしてドレスに刺繍された花は、「若々しさ」をそれぞれ象徴しています。
そして右手には「虹」。変ったアイテムですが、これは「神との契約」を意味しており、それを握らせることで、女王の偉大さを示しているのです。
王族の肖像画に「よいしょ」はつきものですが、エリザベス1世の肖像画は、まさに「演出」の技がそこかしこに仕込まれています。
常に、若く美しく、そして同時に君主としての威厳を併せ持つ特別な存在、「処女王」エリザベス1世。
ここまでくると、生きた「女神」のようですね。
③しかし、実際は・・・
しかし、絵の中で若く美しく描いてもらえたとしても、現実のエリザベスは生身の人間です。「老い」からは逃れられませんでした。
加齢と共に髪が薄くなってくると、カツラを使用するようになります。その数はなんと80個以上!(毎日付け替えていたであろうことを考えると、なかなかオシャレですね)
しかし、エリザベスにとって、特に深刻な悩みは、肌のトラブルでした。
29歳の時、彼女は天然痘に感染し、生死の境をさまよったことがありました。
幸い、危機は脱したものの、後遺症として、髪が抜け、顔に痘痕がいくつも残ってしまいます。
顔は、白粉を塗って隠すことにしましたが、この白粉が新たなトラブルを呼び込みます。
当時出回っていた白粉は、人体に有害な鉛を含んでおり、それを塗ることで肌の状態は更に悪化。
それを誤魔化すために、更に厚く塗り重ねる、という悪循環に陥ってしまったのです。
また、彼女は、肌をより白く美しく見せるため、顔に蜂蜜を塗り、その上に白粉をはたく化粧法を用いていました。
が、温度が上がると、蜜が溶け、化粧も崩れてしまうために、冬や寒い日でも暖炉には近づけませんでした。
エリザベスといえば、白塗りの顔がトレードマークですが、その裏事情を見ると、なかなか大変だったみたいですね。
女王、という単語から思い浮かぶのは、豪華で、煌びやかなイメージでしょう。
しかし、エリザベス1世が玉座に至るまでに辿った道のりは決して平坦なものではありませんでしたし、王位についてからも、決して安心はできませんでした。
「永遠に若く美しい処女王」のイメージは、エリザベスにとっては、生きていくため、「王としてあるため」の鎧だったとも言えるのではないでしょうか。
しかし、その鎧を着続けることは、精神的にも肉体的にも楽ではなかったでしょう。
一番上に立ちながらも、自分のしたいようには、生きられない。「ありのままの自分」を見せるなど、もっての他。
そうした悲しみやジレンマが、白粉の下には塗りこめられていたのかもしれませんね。
文=verde
写真=新井まる


【展覧会概要】
ロンドン・ナショナル・ポートレートギャラリー所蔵
「KING&QUEEN展 ー名画で読み解く 英国王室物語ー」
会期:2020年10月10日(土)~2021年1月11日(月・祝)
※会期中無休
開館時間:10:00~17:00 1月1日を除く金曜日は10:00~20:00
会場:上野の森美術館
(〒110-0007 東京都台東区上野公園1-2)
※入館は閉館の30分前まで
※会場にて午前10時より当日券を販売。入場前日午後5時まで日時指定券の事前販売あり。

参考
・高橋裕子、『イギリス美術』(岩波新書)、岩波書店、1998年
・木村泰司、『知識ゼロからの肖像画入門』、幻冬舎、2015年
・渋谷ファッション&アート専門学校 https://www.shibuya-and.tokyo/
※展示会場内ではプレス内覧会にて許可を得て撮影しています