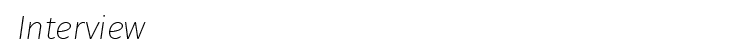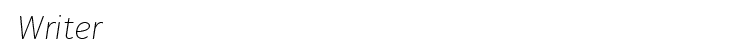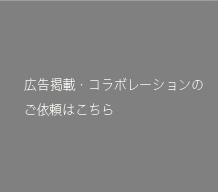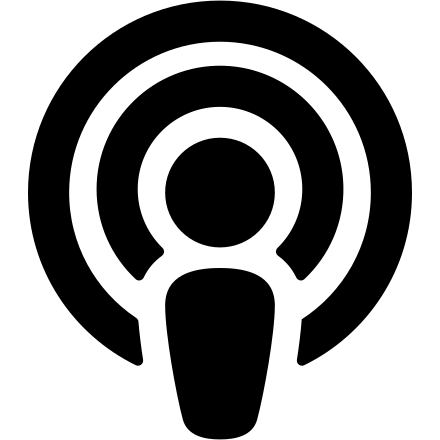青木涼子さんインタビュー 前編
心惹かれることに素直に向かう。葛藤しながらも自分の道を見つける
世界的に活躍する作曲家とコラボレーションし、日本が誇る伝統文化である能と現代音楽を掛け合わせるなど、先進的な創作活動を行う青木涼子さん。彼女はこれまで男性が舞台に立つことが暗黙のルールだった伝統的な能の世界から抜け出し、現代音楽の世界に進出することで、自らの道を切り開いてきた。試行錯誤をしながら、自分が本当にやるべきことを見つけていく姿は美しくしなやかだ。彼女は、なぜ能に魅せられ、能で表現するのか。その原動力は一体どこにあるのか。
前編は、青木さんが能と出会い、新しい表現の可能性を追うようになった経緯を伺う。

能と出会ったきっかけは、なんとテレビ!
girls Artalk(以下、gA):能が日本の伝統芸能だということは知っていても、私たちにとってあまり親しみがないもの。青木さんが能と出会ったきっかけはなんだったのでしょうか?
青木涼子さん(以下、青木さん):幼少期から芸術が好きで、特に舞台芸術を好んでいたんです。小学校の頃は大分県の佐伯市に住んでいました。それこそ、地元の文化会館で親子劇場を観に行くのを楽しみにしているような子でした。自分でも何かやってみたい!と思って、地元の小さいバレエスクールでバレエを習い始めました。田舎なので、美術展だとかバレエの劇団が来ることもなく、都会に憧れていました。
中学生の頃に大分市に移ってからも、バレエを続けていたんですが、ある日、テレビで能をみて、すごく興味が湧いたんです。同じタイミングで、大分市にある市立の能楽堂で初心者向けの能のグループレッスンの募集を見かけて。「お月謝も安いし、ちょうどいい、やってみよう」と、まずは通うことにしました。通っているのは、おじいちゃん、おばあちゃんとか。同年代が全然いない環境で、珍しいと言われながら通っていましたね。
gA:なぜ、能に興味を持ったのですか?

©Junichi Takahashi
青木さん:初めて能をテレビで見たときに、音楽と一緒に派手に舞っていたのが印象的で、かっこいい!こんな風に動いてみたいと思ったんです。 でも、グループレッスンで最初に習ったのが謡(うたい)「謡はいいです」って言っても、謡は必修だからと言われて「声を出す予定はない…」みたいな感じでやり始めたんです。
gA:最初は舞をやりたいと思って始めたのに、全く興味のない謡をやるとなった時、抵抗はなかったのですか?
青木さん:抵抗がなかったと言えば嘘になります。多分、当時は自分の中では、さほど音楽に興味がなかったんです。ピアノを演奏することも、歌ったりすることも、縁がないことだと思っていたみたいで。でも必須だと言われたので、やるしかないですよね。
諦める時は潔く。バレエを辞め、能を選んだ理由
gA:青木さんは、なぜバレエをやめて能の道に進んだのでしょうか?そのきっかけを教えてください。
青木さん:はじめは能をお稽古として、バレエと並行して学んでいたんです。でも、学業や色々なことに時間を取られると、バレエの実力も伸び悩んでしまって。大好きだったんですけど、上手でもなかった。
バレエを続けるかどうしようかと悩んでいた中学3年生の時、高校1年生になる前の春休みに、短期留学のプログラムがあって、記念みたいな感じで友達と参加したんです。
首都圏の同年代の女の子たちも参加していて、皆でロシアに行きました。日本の都会の子たちと出会ったのも刺激的だったのですが、一番衝撃だったのが、若干7歳とかで全ロシアから集められて来た10人が、足を出すだけのレッスンを1時間くらいやっているのを見た時「ああ、もうこれは無理だ」と思い至って。
その時、ディアナ・ヴィシニョーワが在校していて、やはり段違いに上手くて。「うわ〜この子すごい!」と思ったら、彼女はその後、ローザンヌ国際バレエコンクールで金賞をとって。こんなにレベルが高い中でも一握りしか一流になれないんだ、とさらに痛感したんです。

gA:私も幼少期からバレエをやっていて、自分の実力に限界を感じてやめた経験があって、とても共感します。バレエ団には入れるだろうけど、世界には行けないなと中学生の時に思って。もしかしたら、多くのバレエを学ぶ女性がその頃にこういった挫折を経験しているのかもしれませんね。
青木さん:そう。趣味で続けるのもいいけど、なんだか意味がないなあと思って、辞めることにしました。それで、日本人だから日本の伝統的なことをやりたいな、と能に絞ったんです。
芸大時代の葛藤
gA:その後、東京芸術大学に進学した青木さん。大学生活はどうでしたか?
青木さん:東京芸術大学の音楽学部邦楽科に進みました。受験科目の中に、西洋音楽の楽典の試験もあり、当時は関係ないから受験のためだけにやろう、といった感じでした。現代音楽をやるようになるとは思っていなかったので、「ああ、真面目に勉強しておけば良かった!」という思いがあります。
gA:今となってはオペラをやるくらいですものね。
青木さん:その頃は能だけに一生懸命で、西洋音楽は関係ないや!と思っていたんですけど、後悔しています。西洋音楽と密接に関わる活動をするようになったので。
gA:いつから現代音楽と融合して新しいことをやろうと考え始めたのですか?
青木さん:学部の4年生ぐらいのときかな。学内のプロジェクトで色々な分野の学生と一緒に取り組むようになったことが始まりです。伝統を守るというよりは、伝統を活かして新しいものを生み出すことにずっと興味があったんです。
でも、その時はまだまだ「能は現代音楽とは違うもの」というのが前提で、現代音楽に舞をつけて下さいと頼まれる形が多かった。そういった例は1960年代~70年代にすでに存在していました。それに、能の舞もパターンが決まっているので、この音楽にこのパターンを合わせただけ、終わり。みたいな(笑)そんな「異分野の人たちとをやってみた」というコラボレーションにとどまる状況を打開して、新しい表現として発展できるものを作りたいと強く思うようになりました。
後世に残るクリエーションの手法探し
青木さん:なぜ現代音楽と能の舞の組み合わせだと新しいものが生まれにくいのか。それを考えてみると、能の舞って抽象化されていて語彙が少ないからなんです。バレエとか日本舞踊とか、言葉がない芸術だと動きの表現が豊かになるじゃないですか。
能は謡で色々な場面の状況を表現して、舞は抽象的にやって、観ている人に想像させるという芸術なんです。結果、語彙が少ないので、他の舞踊芸術に比べて、どれも同じように見えてしまうかもしれません。
gA:確かに、能の動きは直線的ですもんね。
青木さん:そうなんです。それに、皆さんのイメージの中でも、能面を掛けた人がステージに出ればそれだけで「能とコラボレーションした!」と思われてしまう。本当は、能楽師は謡をうたわないと片手落ちなのに、なんのためにやっているんだろうと思ったりして。それで、最終的に「謡からアプローチして、新しい音楽を作ってから、それに舞の演出がついた形をやらないと、新しいものは生み出せないんじゃないか?」と考えるようになっていったんです。
現代音楽の作曲家って、実は色々な楽器を使った音楽を作曲しているんです。和楽器でも、尺八だとかお琴とか。でも、能に関しては音楽に舞をつけるだけで、謡の作曲まではなかったんです。
gA:それが現代音楽の作曲家に能の謡を作曲してもらうというアイディアの始まりだったのですね。それは学部の4年生くらいの時に考えていたのですか?
青木さん:当時はそういう技術も機会もなかったので、できなかったんですけど、ぼんやりとそういうことには気づいていて。
歴史を振り返ってみると、演劇の分野では演出家が、能楽師や、能のテクニック、コンセプトを取り入れて舞台を作っていたことがあります。鈴木忠志さんは70年代から今も続けられているし、ピーター・ブルックやロバート・ウィルソンも能にインスパイアされて作品を作っていました。
そういう巨匠たちとのコラボレーターは、上の世代で日本の伝統分野の方がもうすでにいらっしゃるし、私が入る隙間がないなと。だったら、まだ誰もやっていない音楽分野でやったらいいのかなと思った部分があります。

新しいことに挑戦するための原動力
gA:そこから、能と現代音楽の新しい手法を考えだして、実践し続けてきたと思うのですが、男性が主流の能の伝統から女性として新しいものを生み出すことは、とても大変なことだと思います。青木さんが、能の新しい表現手法を探求し続ける原動力はどこにあるのでしょうか?
青木さん:能という芸術が好きで、その伝統を基に、いかに新しい芸術を生み出すかというのに興味があるんだと思います。
日本にいると、特に若い時は、自分の意見を発信する機会がなかなか与えられない。大学院の博士課程でロンドンに行って、外から日本を見た時、自分が伝統に縛られていたことに気がついて。能の伝統を継続させるためのシステムに疑問を持つようになりました。原則的に、能は家の人でなくても女性でもできるものだけど、日本にはいわゆる「暗黙の了解」みたいなものがあって。黙っていることが美徳とされるのが一切通用しない、ロンドンのような世界に行ったら、存在しないのと一緒になってしまう。日本にいる時、自分は主張している方だと思っていたけど、全く足りていなくてショックでした。
gA:その時の衝撃も原動力の一部なのかもしれませんね。
前編はここまで。後編では青木さんが見つけだした、現代音楽と能による新しい表現手法をどのように確立していったのか、そしてプライベートでの新たな挑戦についても掘り下げていく。
テキスト:宇治田 エリ 写真:新井 まる
プロフィール

©Hiroaki Seo
青木涼子(あおきりょうこ) 能×現代音楽アーティスト
東京藝術大学音楽学部邦楽科能楽専攻卒業(観世流シテ方専攻)。同大学院音楽研究科修士課程修了。ロンドン大学博士課程修了。博士号(Ph.D)取得。世界の主要な作曲家と協働で、能と現代音楽の新たな試みを行っている。2010年より世界の作曲家に委嘱するシリーズNoh×Contemporary Musicを主催しており、2014年にはデビューアルバム「能×現代音楽」 (ALCD-98)をリリースした。日本だけでなく世界の音楽祭に招待されパフォーマンスを行っている。2013年マドリッド、テアトロ・レアル王立劇場にジェラール・モルティエのキャスティングのもと、ヴォルフガング・リーム作曲オペラ《メキシコの征服》(ピエール・オーディ演出)のマリンチェ役で好演。平成27年度文化庁文化交流使。あいちトリエンナーレ2016参加アーティスト。2017年春の三越伊勢丹JAPAN SENSESのメインヴィジュアルに起用。 2017年12月にはパリ・フェスティバル・ドートンヌ、ケルン・フィルハーモニーにて細川俊夫作曲、平田オリザ台本の室内オペラをアンサンブル・アンテルコンタンポランと共に世界初演する。2018年1月にはフェデリコ・ガルデッラ作曲のオーケストラ曲をソリストとしてフィレンツェ五月音楽祭管弦楽団と共に世界初演する。2018年2月にはアムステルダムでロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団と共演する予定である。
ホームページ:http://ryokoaoki.net/