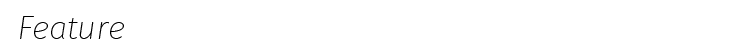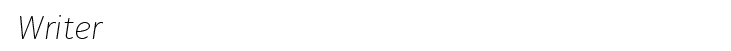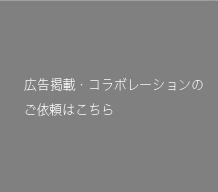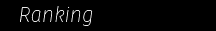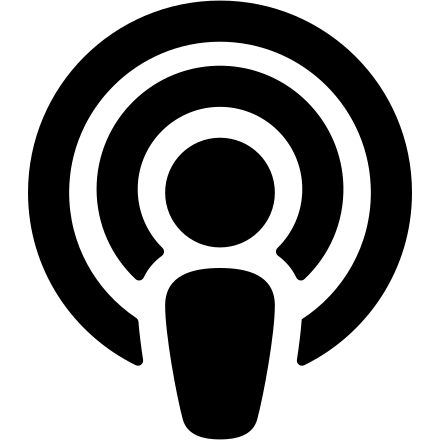未知なるものを求めて 〜石川直樹 写真展「この星の光の地図を写す」
現在、水戸芸術館で開催されている写真家・石川直樹「この星の光の地図を写す」展は、石川氏の20年に渡る活動の集大成ともいえる大規模個展です。

まずは、こちらをご覧ください。

この大きな地図は石川氏が今まで訪れた場所を示したもので、ほぼ地球一周分を歩いていることがわかります。(撮影後、さらに石川氏の訪問した地名が追加されました。)
22歳で北極点から南極点までを人力踏破し、23歳で七大陸最高峰の登頂に成功。当時、この記録は世界最年少でした。
極限の中で世界を撮り続けてきた、石川氏の写真が約450点展示されています。

さらに会場には、石川氏の文章にも触れることができます。
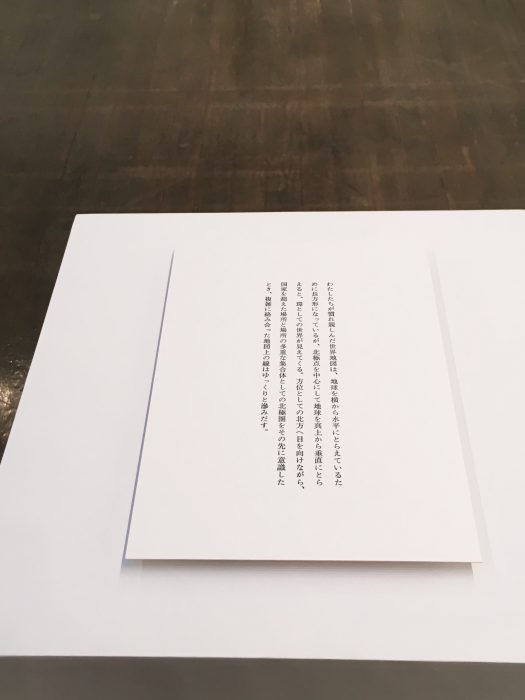
旅先で出会った人々の生活や文化を独自の視点で捉えた文章は、読者を人類の起源に立たせ、人間の本質とは何かを問い正してくれます。2008年には『最後の冒険家 太平洋に消えた神田道夫』で開高健ノンフィクション賞を受賞しました。
写真家であり、作家としても活躍を続ける石川氏は、「石川直樹」という新しいジャンルを確立した人物のように感じます。
そんな彼の軌跡を辿ることは、まさに旅のような体験でした。そして彼が向き合ってきた世界に触れることは、自分達の住む地球との出逢いでもあったのです。
枚数に限りあるフィルムだからこそ、向き合える世界がある
会場は全8室で構成されていて、壁には各シリーズのタイトルが記されています。
第1室は、石川氏の言葉を借りるなら「極地の部屋」。
20歳の時に初めて高所登山を経験した『DENALI』1998、南北アメリカ大陸を縦断した『POLE TO POLE』2000。
過酷な境遇を忘れてしまうくらいの静寂が漂います。
美しい銀山の世界が、真っ白な空間全体で表現されていました。
 『DENALI』1998より
『DENALI』1998より
 第1室「極地の部屋」と石川直樹氏
第1室「極地の部屋」と石川直樹氏
「デジタルは使わない。枚数に限りあるフィルムだからこそ、向き合える世界がある。」
とても印象的だった石川氏の言葉。極限状態に置かれる中で「撮り切ってやるぞ」という執念がシャッターを押すのかもしれません。
また極地の生活にもレンズは向けられています
 『POLAR』2007より
『POLAR』2007より
 『ANTARCTICA』2011より
『ANTARCTICA』2011より
『ANTARCTICA』2011では、変貌を遂げる南極の現在が写されています。
2000年に南極へ到達しそのおよそ10年後に再び南極を訪れた石川氏は、変化し続ける極地の現状を記録におさめました。
銀世界から一転、旅は洞窟の中へと続きます。
『NEW DIMENSION』2007
世界に点在する壁画を撮ったシリーズ。洞窟をイメージした薄暗い展示空間になっています。

『NEW DIMENSION』2007より

『NEW DIMENSION』2007より
最も印象的だったのが、ネガティブ・ハンドと呼ばれる手の壁画。
口に含んだ顔料を吹き掛け、版画のような反転画像の手法が施されています。こうした描き方に石川氏は、「写真の原型を見たようだ。」といいます。
星によって導かれる航路. 芸術とは、そして本当の世界とは–.
旅はカヌーに乗って、原生林へ入っていきます。『THE VOID』2005
部屋には、森の写真と山川冬樹氏によるホーメイの音楽が流れていました。

まず目をひくのは、カヌーのパドル。これは、石川氏が弟子入りした航海士マウ・ピアイルグ氏から譲り受けたもの。

学生時代、石川氏は「スターナビゲーション」のフィールドワークを行ないました。スターナビゲーションとは、まだコンパスも地図もない時代に編み出された、星の位置や自然現象をたよりに航路を導き出すという航海技術。当時、この技術を継承するのはミクロネシアの古老だけでした。石川氏はそのうちの一人であるピアイルグ氏と共に、星だけを目印とする、およそ1000㎞の航海に出ました。
古代の人にとって、唯一の情報源は自然でした。自然と共生しながら生きるための知恵を生みだし、生活の場を広げていったのです。

太平洋に浮かぶ島々「ポリネシアン・トライアングル」、『CORONA』2010より
石川氏が小さな島々を幾度も訪れるのは、その土地に立つことで世界を見回すことが出来るからだといいます。
最も危険で美しい「山のなかの山」K2へ–.
第5室は『K2』2015
K2はカラコルム山脈にある山で、エレベストに次ぐ世界第2位の高さを誇ります。登るのが大変難しいとされ、難易度の高さと美しいフォルムから「山のなかの山」といわれます。石川氏は、2015年にK2への登頂に挑みました。
 『K2』2015より
『K2』2015より
『K2』の展示室は、建築家ユニットdot architectsがデザインしています。K2の地形を3Dデータに起こしそこから山の模型を制作。山を想起させる展示空間になっています。
またこの部屋は天然光が差し込み、模型にやわらかな陰影が出来ます。それが写真とマッチし、K2の空気感に触れることができます。
 『K2』2015より
『K2』2015より
 登山口はパキスタン。2ヶ月におよぶ遠征期間を経て登頂する。『K2』2015より
登山口はパキスタン。2ヶ月におよぶ遠征期間を経て登頂する。『K2』2015より
写真はおおよそ標高順に展示され、山の中を練り歩くように鑑賞者も頂上を目指します。
しかし、石川氏は悪天候に見舞われK2の頂上へは辿り着けませんでした。
会場には当時の映像も流れていて、旅の過酷さが伝わってきました。
 『K2』2015より
『K2』2015より
旅は国外から国内へ.私たちの住む列島の姿を写す
壮大な旅が続き、ちょっとずつ世界の姿が見えてきました。レンズは国外から、日本列島にも向けられています。
世界を知るためには、自分たちの暮らしている土地もまた見つめなければいけません。
『Mt.Fuji』2008
いわゆる、”日本の象徴”というイメージから富士山を切り離し、”登る山”という視点で切り取られた写真たちが、富士山の形に沿って展示されています。
 『Mt.Fuji』2008より
『Mt.Fuji』2008より
無数のツメ跡を残す山肌や樹海が露わとなり、麓では山自体をご神体とするお祭りが催されています。「山」に対する日本独自の文化に触れることができました。
日本もまた、島々の繋がりで出来ている
石川氏は、列島の南北に点在する島々へ幾度も足を運んできました。そこで撮りためた写真たちが、長い回廊に北と南とに分けられ、展示されています。それが、新作を含めた『ARCHIPELAGO』2009-
 『ARCHIPELAGO』2009-より
『ARCHIPELAGO』2009-より
南はトカラ島、奄美、沖縄、宮古、八重山、台湾など、
北は青森や北海道、周辺の離島からサハリン島、クイーン・シャーロット諸島などを訪れた、計110点の写真たち。
その向かいに展示されているのは、島々や日本海側の北陸・東北地方に古くから伝わる来訪神信仰へ焦点を当てた『MAREBITO』2009-シリーズ。
 「まれびと」は民俗学者の折口信夫氏による用語。霊的な存在を指す。『MAREBITO』2009-より
「まれびと」は民俗学者の折口信夫氏による用語。霊的な存在を指す。『MAREBITO』2009-より
「日本列島の沿岸には、異質な他者を畏れながらも迎え入れる文化が残っている。」
仮面が登場する祭祀儀礼を訪れる中で、そう強く感じたという石川氏。
得体の知れないものを受容する文化。その習わしに従って、石川氏自身も現地の人たちに温かく迎え入れられ、こうして写真に残すことができたのです。
中高生たちの日常. 子供たちが自分で写したTIMELINE.
そして、日本最後の旅は福島へ–。
『TIMELINE』2016 と名付けられた部屋には、福島の中高生たちと劇作家の藤田貴大氏、音楽家の大友良英氏、振付家の酒井幸菜氏と共にミュージカルをつくるプロジェクト『タイムライン』の様子が紹介されています。そこには映像と石川氏が中高生たちの通学路を撮った写真、そして彼女たちがインスタントカメラ「写ルンです」で撮ったスナップ写真が、散りばめられていました。
 『TIMELINE』2016より
『TIMELINE』2016より
毎日、SNSでタイムラインを投稿する彼女たちにとって、現像されるまで中身がわからないインスタントカメラはどう写ったのでしょうか。そして出来上がった写真を見て、日常の中からきっと新しい発見があったのだと思います。
旅の終わりに. 石川直樹のこれまでとこれから
いよいよ旅は終盤に差し掛かりました。
写真だけではなく、石川氏のプライベートな道具たちであふれた『石川直樹の部屋』。
これまでの遠征に欠かせなかった、石川氏の貴重な旅道具たちが特設空間に敷き詰められていました。
 dot architects設計
dot architects設計
 当時の思い出などが直筆のメモで添えられている。
当時の思い出などが直筆のメモで添えられている。
特に印象的だったのが、2004年に熱気球で太平洋を横断中に着水した、当時のゴンドラに残った私物たち。驚くことに、これらは海を渡って遥か遠くの日本の離島へたどり着き、島民からの連絡を受け石川氏が回収したものです。
さらに、石川氏がこれまで読んできた本や子供の頃の写真なども展示され、石川氏の原点を体感することができました。
 とても気さくな石川氏。その人柄も大きな魅力。
とても気さくな石川氏。その人柄も大きな魅力。
こうして、地球一個分を旅してまいりました。
石川氏が向き合ってきた世界は、地図帳や地球儀では覗けない、テレビにもインターネットにも載っていないものばかり。
大切なのは、自分の目で知ろうとすること。本当の世界を自分の肌で感じ得ることなのだと、知ることが出来ました。
– なぜ、旅に出て写真を撮るのですか?–
「未知なるものを見たいから。」
石川氏が写真で描いてきた世界地図は、きっとこの先何年も何十年も、一つの指針として人々を照らし続けてくれるでしょう。そして、私たちが住む星はなんて美しいのだろう、と石川氏は優しく教えてくれるのです。
今の時代だからこそ、触れるべき世界の姿がそこにあります。まるで本当に旅をしているような、はじめての感覚で体験できた石川直樹氏の写真展。
壮大な冒険に、あなたも出てみませんか?
文章、写真:多田愛美
〈展覧会情報〉
石川直樹「この星の光の地図を写す」
●会場:水戸芸術館現代美術ギャラリー
●開催日:2016年12月17日[土]~ 2017年2月26日[日]
●開館時間:9時30分~18時(入場時間は17時30分まで)
●入場料:一般800 円、団体(20名以上)600円
中学生以下・65歳以上・障害者手帳をお持ちの方と付き添いの方1名は無料
※一年間有効フリーパス
・「ハイティーンパス」(15歳以上20歳未満 ):1,000円
・「おとなのパス」(20歳以上):2,500円
●主催:公益財団法人水戸市芸術振興財団
●助成:公益財団法人野村財団
●協賛:株式会社集英社
●協力:アサヒビール株式会社、産経新聞社、SCAI THE BATHHOUSE
●企画担当:竹久侑(水戸芸術館現代美術センター学芸員)
〈関連イベントが開催されます。〉
石川直樹×森永泰弘 VJ+DJイベント「惑星の光と声」
石川直樹とサウンドデザイナーの森永泰弘が、世界各地でそれぞれ撮影/録音した写真と音源を使って、初のビジュアル&ディスクジョッキーイベントを行います。
●日時:2017年2月12日(日)14:00~15:00(13:30開場)
●会場:水戸芸術館ACM劇場
●出演:石川直樹、森永泰弘
●観覧料:全席自由 当日1000円、前売り800円
※未就学児は入場できません。
【チケット取扱い】前売り券完売/当日券あり
・水戸芸術館エントランスホール内チケットカウンター
・チケット予約センター(9:30~18:00 月曜休館) TEL: 029-225-3555
・水戸芸術館ウェブ予約 http://www11.arttowermito.or.jp/tickets/ticket.html
〈お知らせ〉
石川直樹写真集『この星の光の地図を写す』 3月発売予定
水戸芸術館1階ミュージアムショップ コントルポアンにて予約受付中
予価:本体3,700円(税込3,996円)
〈アーティスト情報〉

【石川 直樹 略歴】
1977年東京生まれ。写真家。
東京芸術大学大学院美術研究科博士後期課程修了。
人類学、民俗学などの領域に関心を持ち、辺境から都市まであらゆる場所を旅しながら、作品を発表し続けている。
『NEW DIMENSION』(赤々舎)、『POLAR』(リトルモア)により、日本写真協会新人賞、講談社出版文化賞。『CORONA』(青土社)により土門拳賞を受賞。著書に、開高健ノンフィクション賞を受賞した『最後の冒険家』(集英社)ほか多数。最近では、ヒマラヤの8000m峰に焦点をあてた写真集シリーズ『Lhotse』『Qomolangma』『Manaslu』『Makalu』『K2』(SLANT)を5冊連続刊行。最新刊に写真集『DENALI』(SLANT)、『潟と里山』(青土社)、『SAKHALIN』(アマナ)、著書『ぼくの道具』(平凡社)がある。